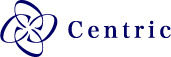プロCFOインタビュー
Professional CFO Interview
「グローバルとPE投資先の現場で磨いたCFOとしての覚悟と実践」 ― 数字で事業を理解し、成長を描き、実現する ―

Kito Crosby
Executive Officer APAC CFO
宇佐美健史様
1994年4月 株式会社あさひ銀行
1995年4月 アイビー建販株式会社
2003年6月 Deloitte&Touche LLP
2006年10月 Bridge of Brains株式会社
2009年7月 株式会社アニージングゴルフ(代表取締役)
2012年3月 Tachibana & Ochiai Professional Corporation
2013年9月 住友林業株式会社
2019年7月 株式会社荏原製作所
2021年5月 (JIS投資先)曙ブレーキ工業株式会社(執行役員CFO)
2024年12月 (KKR投資先)Kito Crosby(Executive Officer APAC CFO)
―これまでのご経歴を簡単に教えてください
兵庫県立大学を卒業後、銀行に就職しました。当時はバブル崩壊直後で金融危機の入り口という厳しい時代でした。商社と銀行で最後まで迷いましたが、銀行なら幅広い業務を経験できるだろうと考えて選びました。ただ、入行してみて「ここで一生食っていくのは難しい」と強く感じました。学生時代から漠然と「いつか海外で活躍したい」という思いを持っていたこともあり、海外で通用する専門性を身につける必要性を痛感しました。
その後、家業を経てアメリカへ留学し、ビジネススクールで会計学の修士号を取得。ニューヨークのDeloitteに所属し、日本企業の在米子会社監査、アメリカ企業の監査等を担当しました。当時所属していたニューヨークのJapanese Service Groupには100人規模の日本人が在籍し、日本人以外の多様なバックグラウンドを持つ人たちと働いた経験は、自分にとって大きな財産です。その後、日本企業の経理財務ポジションを経て、プライム上場の自動車部品製造会社のCFOを務め、2024年12月から現職のキトークロスビーグループのAPAC地域を統括するCFOに就任しました。
―CFOを目指すようになったきっかけは
ニューヨークの監査法人に勤務していた際、同僚や先輩が事業会社に転職し、コントローラーを経てCFOを目指している姿を間近で見ました。アメリカではCXOという概念が当たり前で、会計学を専攻した学生が監査法人に入り、その後CFOを目指すルートは一般的でした。日本では「会計士はずっと監査法人」という常識がありましたが、自分も「会計士で終わるのではなく、事業に関わるCFOを目指すべきだ」と気づいた瞬間でした。
―米国留学を決断された背景
1994年、銀行で働き始めた当時はバブル崩壊後で、借金だけが残るような状況を目の当たりにしました。このままでは金融業界では生き残れないと考え、より専門性を磨く必要があると決意しました。日本の枠を超えて海外でも通用する力を持つべきだと考え、米国留学を選んだのです。
―キトークロスビー入社の決断理由
近年、日本企業の進出先はアメリカよりも東南アジアやインドにシフトしており、私自身もそうした地域での関わりが増えていました。そんな中、キトークロスビーは米国クロスビー社との統合企業であり、株主はKKRという世界有数のPEファンド。米国との関わりも強く、自身のスキルを最大限活かせると確信しました。
選考過程では日本子会社の責任者との面接後、アメリカ本社での面接がありました。オファー前に現地でディナーの場が設けられ、チームの人たちと腹を割って話し、「この人たちと働けるなら魅力的だ」と確信しました。1泊3日の強行スケジュールでしたが、入社を決意する大きな要因となりました。
―現在のCFO業務と前職との違い
APAC地域内での財務報告、月次予実管理、グループ会社や経営陣との連携、四半期ごとの米国本社会議対応、本社への定期・不定期報告などが主な業務です。さらに財務基盤の強化や業務効率化も進めています。前職の曙ブレーキ社ではグローバル本社CFOとしてファンドと直接やり取りしていましたが、現職ではAPAC地域のCFOとして「子会社の立場」で報告する点が大きな違いです。そのためファンドの意図が見えにくい部分もありますが、前職で直接やり取りをした経験が今大きく役立っています。
―外資ファンドと日系ファンドの違い
アメリカのファンドは明確でリードが強く、失敗を恐れずに攻め続ける文化を持っています。日本では「失敗は許されない」という社会的な風潮がありますが、アメリカでは「ベストを尽くした結果ダメなら再挑戦できる」という仕組みが存在します。この違いはファンド運営や企業カルチャーに色濃く現れています。
―人材マネジメント・カルチャーづくりで意識していること
PEファンド傘下企業になると社員が不安を感じ、人材流出が起こりがちです。そのため「ファンドが入ることは企業価値向上につながる」という点を明確に伝えています。前職では四半期ごとに動画配信を行い、工場を定期的に訪問して直接説明するなど、徹底したコミュニケーションを重視しました。特に「ファンドの意図を丁寧に翻訳して伝える」ことは、社員の信頼を得るうえで非常に重要でした。
―学び・インプットの方法
海外メディアや国内外の知人とのネットワークから最新情報を得ています。会計士・弁護士・金融機関・コンサル・IT企業など幅広い層と交流を持ち、現場の情報を得ることを大切にしています。また、社内キーパーソンと1on1で話す機会を設けるなど、自社理解を深める努力も欠かしません。
―苦労と乗り越えた経験
アメリカから帰国し日本企業に入った当初、旧態依然とした働き方に直面し、評価も得られない時期がありました。それでも「日々挑戦」と自らに言い聞かせ取り組んできました。外資ファンドが参入するようになった近年では、国際経験を持つ人材の評価が高まり、風向きが変わってきたと実感しています。苦しい時期も「日本企業を世界で成長させる使命感」で踏みとどまりました。
―キャリアでブレない軸
「常に成長を目指し、プロフェッショナルであること」です。プロフェッショナルとは「期待値を正確に理解し、それを上回る成果を出し続けること」だと考えています。また、「尊敬」と「感謝」を大切にしてきました。特にロサンゼルスで出会ったTakenaka Partners創業者・竹中征夫氏は、自分のメンター的存在であり、日本とアメリカの架け橋として活動する姿に強い影響を受けました。泥臭い仕事も厭わず、志を持って取り組む姿勢は自分の指針となっています。
―「こうしておけばよかった」と思うこと
2006年にニューヨークでの仕事を辞め、家業をサポートするために日本へ帰国しました。そのままアメリカでキャリアを続けていたらどうなっていただろう、と今でも思うことはあります。ただ、その経験があったからこそ、日本と海外を行き来するキャリアに繋がったとも考えています。
―ファンド投資先CFOに必要なスキル・マインド
CFOへの期待値を正確に理解することが最重要です。株主やCEOだけでなく、PEファンドの期待も加わります。財務・会計の専門知識はもちろん、多方面とのコミュニケーション力が必須です。組織が小さい場合はハンズオンで現場に入ることも求められます。
―今後の成長領域
日本とアメリカ以外の国々への理解を深めたいと考えています。中国・韓国・東南アジア・インド・中東・アフリカなど、多様な国との関わりを通じて学びを得ることが自分の成長につながると信じています。新しい文化や人に触れることで、ビジネスにおける調整力やイノベーション創出にも役立つはずです。
―将来展望・CEOキャリアについて
これまでにCEOの打診を受けたこともありますが、最も大切にしているのは「自分が最も求められている場所で力を発揮すること」です。安定した大企業よりも挑戦のある環境にこそ、自分の経験が生きると考えています。CFOかCEOかは肩書きの違いに過ぎず、周囲から必要とされる場であれば全力を尽くすというスタンスです。
―CFOを目指す方へのメッセージ
「スーパー経理財務部長は要らない」という言葉をよく耳にします。CFOは数字を通じて事業を理解し、成長を描き、それを実現する役割です。経理・財務業務とは似て非なるものです。そのため、多様な職場や海外経験を積むことがCFOとしての引き出しを増やします。何よりも「仕事を通じて成長したい」と考える方にとって、CFOは非常に魅力的でチャレンジングな仕事だと思います。
無料転職支援サービス
申込フォーム
(目安時間1分)