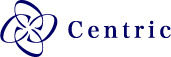プロCFOインタビュー
Professional CFO Interview
責任と自由度を抱えて企業のかじ取りをする経験は、スタートアップにも一般事業会社にもない妙味が有り
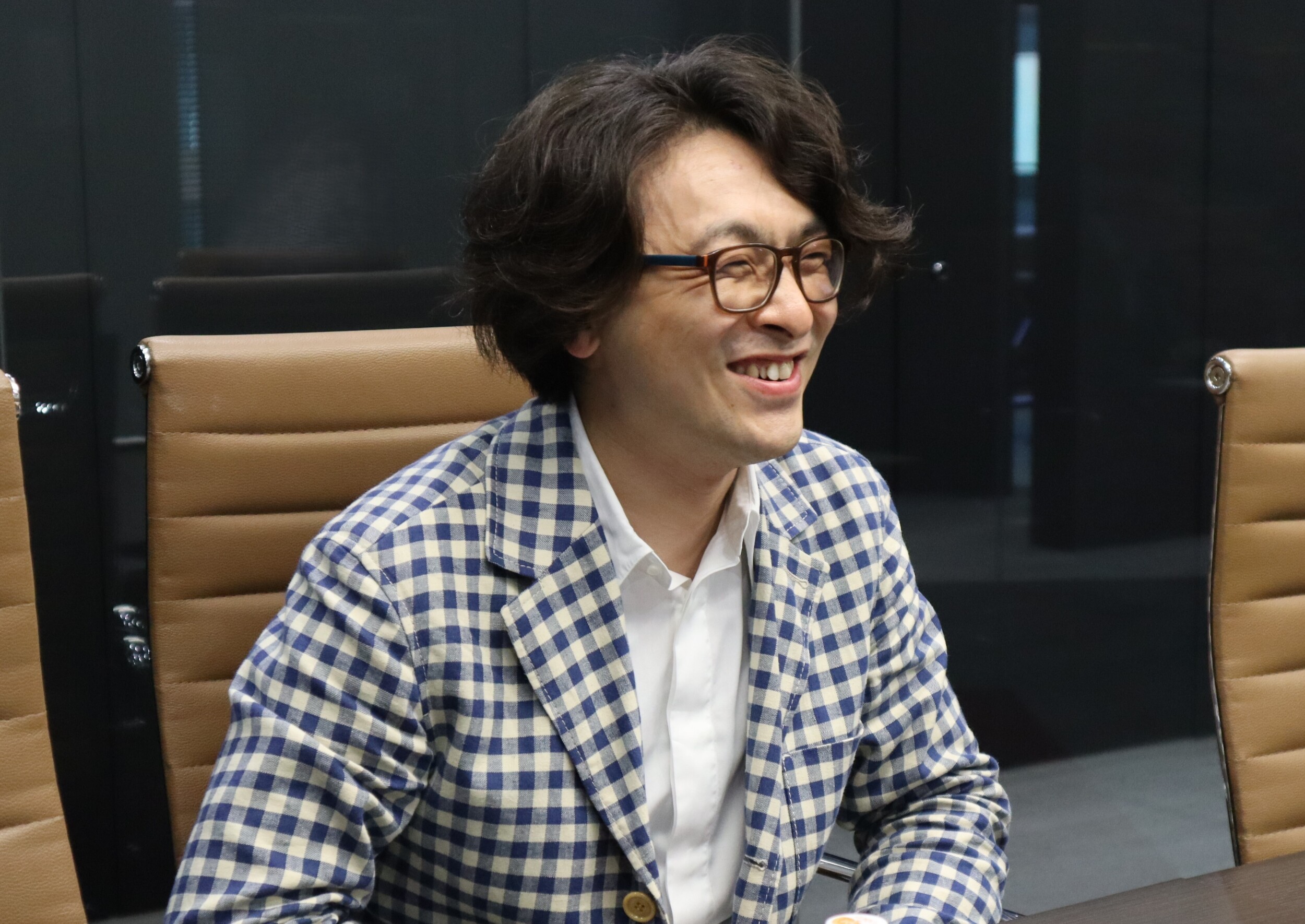
J-CEP株式会社
CSO
古城隆文様
2014年 (株)ローランドベルガー入社
2018年(ポラリスキャピタル投資先)(株)BAKE 経営戦略室長
2022年 スタートアップ企業 取締役CFO
2023年(ロングリーチ投資先)J-CEP株式会社CSO
―どんな学生時代を過ごされたのでしょうか
高校卒業後に8年の学生生活を送っています。社会に出るのがとても嫌でした。
そんなダラダラした学生生活の反動で、今の激動の職務遍歴が形成されているような気がしています。
最初に入った大学はわずか1年で中退しました。薬学部に入学したのですが、自分の興味領域が理学領域(基礎研究)に近かったことと、高校同窓で浪人中の友人に「東京に先生一人で教えている東大合格率100%の面白い塾を見つけたから来ない?」などが重なり、ノリでやめてみました。どうしても、面白そうなコトに流れがちな性格です。
大学では、本ばかり読んでいました。大学生協の書籍部や図書館に入り浸り、読書会を開くなどしていました。ちなみに大学の専攻は政治学で、修士時代の研究テーマは、「投票行動」です。同じ文系学問でも、法律学などには興味がわきませんでした。
折角大学で学ぶのだから、自学自習が困難なものを選びたいという思いも強かったことに加え、祖父が田舎の議員であったことが影響しているかもしれません。祖父を間近で見ていた経験から、政治学の中でも、投票行動を研究することにしました。自分は政治の執行側には縁がなさそうと思っていましたが、他方で、政治を客観的に観察者として研究することは、自分にもできそいだと考えたことが影響しています。
-ご自身の若手時代で特に印象的だった経験、意識されてきた点はどういった事だったのでしょうか。
なにか1つのことを突き詰めていく、ということが非常に苦手なのは自覚していたので、「求められる最低ラインをとりあえず超えておくこと」と、「その環境で希少性の高い能力を磨く」ことを考えていました。
新卒で入ったのは戦略コンサルティング業界で、求められる最低ラインが全方位的でかつ高いため、リサーチ・PPT/Excel資料作成・プレゼンテーションなどビジネスマンとしての基礎は一定そこで獲得できたかなと思います。
加えて、クライアントやチームメンバーに伴走し、寄り添うということも意識していました。これはビジネスマンとして本質的に求められる能力であると考えていますが、若手レベルでは、そもそも困難ですし、深く求められない領域と考えます。自分はそこについて意識を高めることで、差別化を図り、評価やお付き合いの場をいただいた経験があります。そのような過去から、私は「物事を相手の物差しで考えること」および「相手と自分の考えた方向性が合致するところまで対話すること」この2ステップを仕事における基本的なスタンスにしています。
また、自分の性格として、「一点集中は苦手で、気分にムラがある」ことを自覚していました。ですので、とにかくその時点で興味が持てる仕事にアサインしてもらうべく、RB社の消費財・流通チーム(CGR)の担当オフィサーと顔を合わせるたびに、「案件に入れてください!」とお願いしていました。結果としてアパレルや飲食など幅広な経験を積むことができ、自身の転職キャリアのアーリーステージにもつながったと感じています。
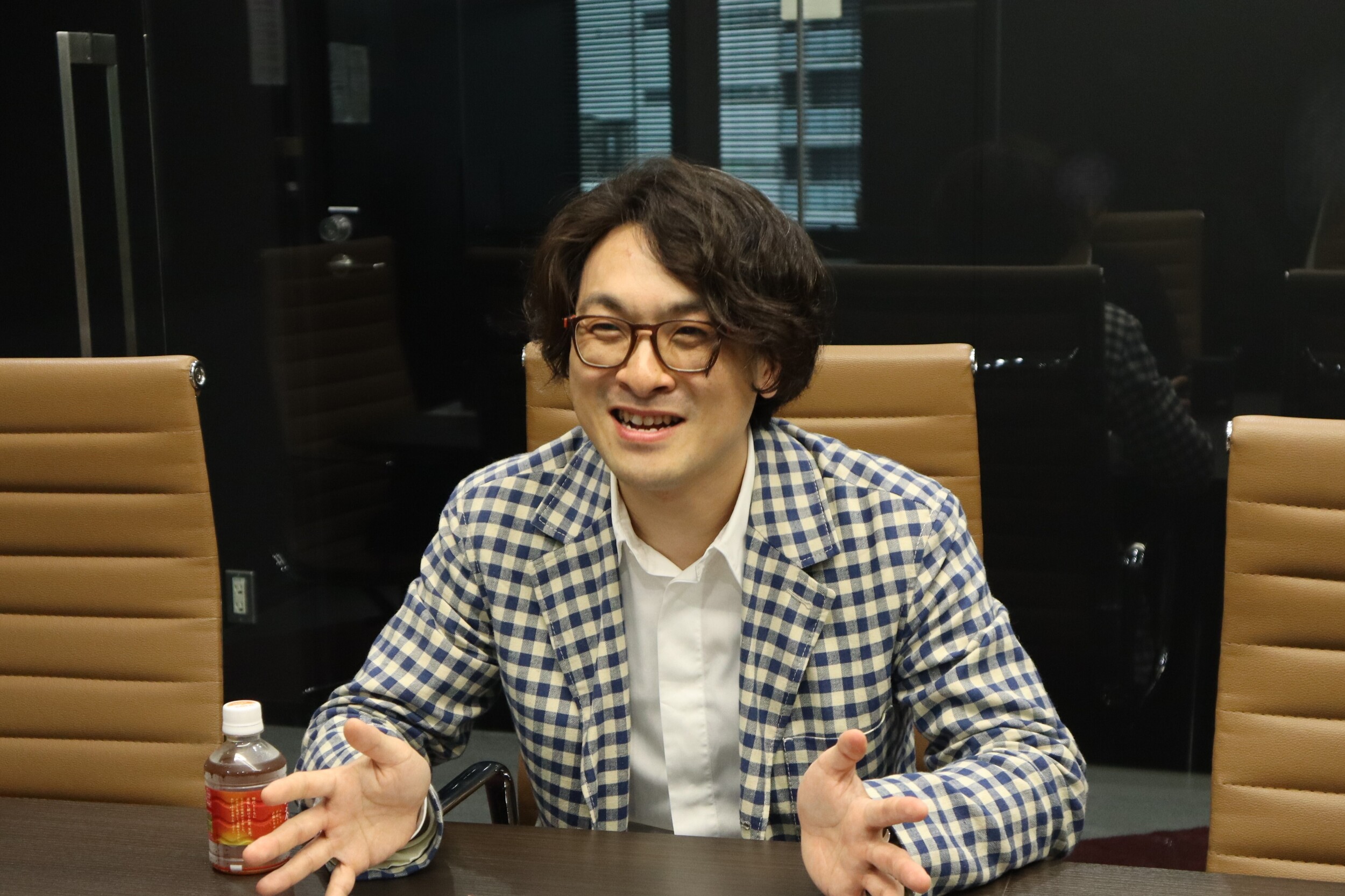
-若くしてCxOを務められておりますが、自身のどういった部分が評価されたと感じますでしょうか。
ジェネラリストにしては、そこそこ深みがあるということに尽きると思います。
そこそこ深いというのは過去携わったタスクにおいて、もうちょっと知りたいなと思って自主的に調べた内容が自分の中に蓄積されているようなイメージです。
契約書ひな型を何となく作れる、が普通だとすれば、一歩踏み込んで「どれが形式的/実質的効力を持つ条項なのか」を理解および追及しようと普段から繰り返し考えるようにしています。 そうすることでマーケットにいそうでいないポジションに自分が入り込めた実感が確かにあります。そこそこ深いジェネラリストというのは、リスクが高い選択であるかのようにも思いますが、意識的に志向していけば、市場価値のある領域と考えます。
要すれば、何かしらで突き詰めた専門家になる方向を選べなかった一方で、そのぶんマルチプルに動けることを志向し、一人いれば8掛けくらいで何でもこなせます。できないとは言わないです、と大真面目に言えるだけの経験を積めたことに、レアリティがあるのかなと考えています。
その点で言えば、説得力のある発言をジェネラルに行っていくためには、多様な経験を踏まえた自分の確固たるスタンスを確立することが重要なのかもしれないと思います。たとえば会計士の方であれば、会計事務所だけでも十分食べていけるのに、敢えてそれを捨てて事業会社で経理含めた実務経験を積む、みたいな話が良い例で、コンサルだとそれが実業・事業会社での現場への没入だったりするのだろうなと思います。
-PEファンド投資先の(株)BAKEから次の機会としてスタートアップ企業を選ばれたご理由について確認させてください。
創業から3年も代表に声をかけ続けられており、待たせるのも心苦しくなって人情で入社を決めました。
もともと一人のユーザーとしてサービスを利用しており、会社の良いところも悪いところも一定分かっている状況は非常に良かったです。BAKEをやめる積極的な理由はあまりなかったのですが、BAKEがコロナによる危機をしのぎ、事業継続への道筋が見えたことは一つのきっかけとして大きかったと思います。
-戦略コンサル出身でファンド傘下プロ経営者として活躍されている方は多くいらっしゃいますが、戦略コンサルでの経験はファンド傘下でどのように生きていると感じますか。
同じファームを卒業された方に共通しているのは、コミットメントの高さかなと思います。どうやったらできるかを自分事として考える癖は、ビジネスマンとしての基礎能力以上に重要なのだなと感じます。それ自体がさまざまな能力やキャッチアップのスピードを圧倒的に高める、コアコンピタンスなのではないかなと考えています
業務経験とは毛色が若干異なりますが、人的なネットワークもとても大切です。業界知識の吸収や経営全般の相談において、諸先輩方からのご助言ほどありがたいものはないです。人的なネットワークを作るときに心掛けていることは、社内であれば、困りごとや自分に対する興味関心をいかに拾えるかです。これができるか否かが、ネットワーキングのキモだと思っています。
自分も困ったことがあれば、ファーム時代の先輩方に折に触れてご連絡をし、近況報告からスペシフィックな話も相談し、培ったネットワークを活用し、恩恵を受けています。
-現職J-CEP社でCSOとしての主な業務内容について
メインは経営情報の集約および成長戦略・予算の設計です。
企画だけでなく実務サイドとしても、人材確保に向けたアクションの立案実行をハンズオンで行うなど、現場に近い視点から幅広に仕事しています。
-2回目のファンド投資先企業となりますが、前回ファンド投資先企業であるBAKE社の経験が生きている部分が有れば確認させてください。
ファンドごとに特徴があるのは承知しておりますが、共通して株主との対話の重要性は非常に学びとして生きています。BAKE社では予算・中計策定を都合5~6回、ほぼ単独で行ったのですが、経過・状況の共有をこまめに行うことで、結果トータルでの説明コストが下がっていくのを実感しました。在籍後半はコロナで混沌とした期間に突入したのですが、過去のやり取りによる信頼の蓄積で早期に一枚岩となって対応できていたと思います。
また、社内メンバーの補完や他社事例の共有など、ファンドが株主となっているときに特有の株主リソース活用においても、対話コミュニケーションなしにはアクセスできないので、これもまた重要な観点だと思います。どのような方でもお互いの仕事を減らす、あるいはより円滑に進めていくというところで言うとやはり会話がない限りはどうしてもうまくいかないと思います。話さない限りわかりえないですし、対話を重ねてどのような相手でも歩み寄っていく努力をしていく、対話だけでなくて粘り強さも重要ですね。まだまだ至らないところは多いですが、対話に必要な経営状況のモニタリング・レポーティングと関係構築についても、相手の立場に立って「なぜ必要か」を考えることが予めできているので、特に抵抗感もなくなめらかに業務ができています。
-率直にロングリーチについてはどういった印象を持たれましたでしょうか。
非常に合理的で、かつ堅実なファンドという印象です。
ビジネスに対するコミットメントが高く、その分緊張感もありますが、経営陣に対するリスペクトも感じますし、信頼できるパートナーです。
-ロングリーチビジネスパートナーズ(LBP)について感じた事が有れば確認させてください。
単なるバリューアップチームに留まらず、現場が困っていることも積極的に回収していく頼もしさがあります。LBPとは現在週に2回の定例と、特定領域におけるMTGのファシリテーションをお任せしており、基本的にほぼ毎日何かしらの情報共有やMTG同席があります。週2回も定例があるファンドは非常に稀だと思いますし、我々ボードメンバーだけでなくファンドの方が現場に入って情報収集をして提案をしてくれるというファンドは私の知る限りないですね。
課題解決で言えば、ファンド参画直後のリーンな事業計画実現に向けた一丁目一番地としての「見える化」が、現場としてもどこから手を付ければよいのかという状況になっていたようで、先鞭をつけて頂いたところは非常に助かりました。ファンドにおけるバリューアップの初手を忠実にこなしていただいており、これがあるかないかでだいぶやりやすさが変わってきます。
-古城様の今後の展望についてはどういった事を想定されておりますでしょうか。
とにかくいまの任務をしっかりこなすこと、これに尽きます。BAKEの時も前職スタートアップでも、事業拡大までは一定進めたものの、IPOという通過点には残念ながら到達できていないので、信任に応え結果を残したい気持ちです。
さらにその後のことはまだ全然考えていないですが、責任に伴う効力感は嫌いでなはいのだなと分かってきたので、より大きな責任を持てる仕事があれば挑戦してみたいなと漠然と考えています。CEOがヘッドである以上、CSOは横串の機能とならざるを得ず、各CxOがファンクショナルであればあるほど調整役となる傾向にあります。これはこれで楽しく、より事業規模の大きいところでCSO職に就くのも面白いかもしれません。
一方で、純粋に「重い役割」も興味深いと思っています。たとえば単一セグメントの企業であれば「事業責任を持てるCSO」としてCOO兼務という形も広がりはあり得るでしょうし、もっとシンプルに、ピープルマネジメントまで含めた職責としてCEO職に就く、というのも憧れるところです。
独立するパターンとしては、自分だけで会社を興して、というよりは、プレイヤーとしてもう少し大きなことがしたいと考えている方を、経営の観点で支援するような動き方が理想的かなと思います。
-最後にCSO・CFOを目指されている方やファンド投資先に関心を持たれている方にメッセージをお願いします。
もともとビジネスマンとしてしっかり自律されている方にはもちろん、裁量のある仕事がしたい一方で最低限守るべきラインをガイドされた状態が望ましいと考えている方には、ファンド傘下企業はかなりおすすめです。外すべからざる要諦をサポートされながら、責任と自由度を抱えて一つの企業のかじ取りをする経験は、スタートアップにも一般事業会社にもない妙味があります。
ファンド傘下だからといって特段気負う必要はありませんが、ファンドもファンドマンも色々ですから、そのあたりの相性はできるだけ見極められるとよいかなと思います。特性プロフェッショナルファーム出身者であれば、どこのファンドでも2次~3次のつながりまででアプローチ可能なはずだと思っていますが、今回僕はRB時代の後輩がロングリーチにいたので個人的な伝手を活用し、ファームとファンドのリレーションやファンドの特性を確認しました。そのうえで面接では、ファンドというよりも案件担当者が株主として取るべきと考えている立場が、自分のプレイスタイルをつぶさないものか、というところの見極めが結構重要かなと思います。役割定義をきっちり切りたいファンドと、課題探索とつぶし込みを自由度高く行いたい候補者では、かみ合わないこともあると思うのでそこを見極められればいいのかなと思います。
CSOというポジションが用意されていることは、ファンド投資先であってもまだまだ珍しく、いわゆる経営企画ヘッドと、全社のマネジメントとしての戦略担当(=CSO)とでは、まわりからの見え方も裁量も、もちろん責任も大きく異なります。経営企画は実務部隊の後方支援という役回りが多いですが、CSOは戦略を通じて事業をドライブする立場です。事業への深い理解だけでなく、個々のメンバーレベルに渡る目配りと全社全レイヤーの活性化まで、硬軟織り交ぜたスキルセットが求められます。これを楽しめる方は、一介の経企を飛び越えてCSOポジションに就くと、非常に充実した仕事ができるのではないでしょうか。

無料転職支援サービス
申込フォーム
(目安時間1分)