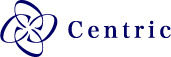プロCFOインタビュー
Professional CFO Interview
領域で誰よりも成果を出す事でCXOの役職がなくてもリーダー・責任者として見られる

株式会社キャスター
取締役CSO
川村尚弘様
2002年12月 University of Oklahoma経済学部卒業
2003年4月 株式会社トーマツコンサルティング入社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)
2006年6月 株式会社NTTデータ経営研究所入社
2008年4月 フロンティア・マネジメント株式会社入社
2013年6月 株式会社ベルシステム24入社(ベインキャピタル投資先)
2015年6月 同社営業企画部部長就任
2016年3月 同社事業企画部部長就任
2016年11月 株式会社ICI石井スポーツ入社(アドバンテッジパートナーズ投資先) 同社執行役員就任
2019年9月 株式会社キャスター入社
2020年1月 同社執行役員就任
2020年11月 同社取締役就任(CSO/CFO兼務、2022年9月よりCSO)
― まず上場承認誠におめでとうございます(2023年8月上場承認、10月4日上場。インタビューは2023年9月実施)。承認を受けた際の率直な感想をお聞かせください
ありがとうございます。ほっとはしています。ただ、すでにかなり前から上場企業にふさわしいガバナンス体制、予算管理、決算体制などは完成されていたと認識しています。むしろ上場準備のプロセスの中でそういった課題を1つ1つ解決していったときのほうが喜びは大きかったかもしれません。45日以内に四半期決算が余裕をもってできる体制になったときの喜びとチームメンバーへの感謝のほうが大きかったです。
-皆さん喜びひとしおという方よりも地道に積み重ねられて最後ほっとされたという感想をされる方が多いですよね(笑)。それでは、ご経歴と自己紹介について確認させてください
大学卒業後、3社であわせて10年間コンサルティングをしていました。企業再生のプロジェクトに多く関与し、その経験の中で経営管理の基本やデットIR、M&Aなどの知見を学びました。その後、PEファンドの出資先での部長職、経営職を経て、現在キャスターで取締役をしています。
-どんな学生時代を過ごされたのでしょうか
高校生の時は、部活でサッカーをしているか友達と遊んでいるかのどちらかで、学生ならではの自由を満喫していた気がします。勉強は苦手というか、ほとんどしていなかったです。特に英語や歴史などの覚えることの多い科目が苦手で、よく追試を受けていたのを覚えています。逆に、数学は比較的得意でした。1つの方程式だけ覚えればたくさんの問題に答えられるので、私にとっては今風にいうとタイパのよい教科でした。学校の行事でも・イベントでも裏方でマネジメントやプランニングを行うのが得意で、企業の裏方でサポートするという分野に興味を持ちました。そんなときに高校の図書館で「コンサルタントになるには」という本を読み、将来はコンサルになろうと薄っすらと考えていました。その後、アメリカで学ぶ事が将来的にコンサルタントとして活躍するために有効なのではないかと感じアメリカの大学に進みました。
アメリカの大学では1-2年生のときは英語での授業についていくために必死で勉強しましたが、3-4年生のときには慣れもあって、またあまり勉強しない学生に戻ってしまいました。ただ、この時に会計学を専攻していた(最終的に経済学で卒業していますが、会計学、MIS、経済学を専攻していました)ことから、ビッグ5(当時)会計ファームに入社したいという思いが強くなり、今のキャリアにつながったのかもしれません。コンサルタントになりたい方はマッキンゼーやボスコンを第一志望にする方が多いかもしれませんが、私はこの2社は受けておらずトーマツコンサルティング(現デロイト)が第一志望で、ほかの志望企業も会計系ファームが中心でした。
-ご自身の若手時代(20代)で特に印象的だった経験、意識されてきた点はどういった事だったのでしょうか。
トーマツコンサルティングに入社した初日に、パートナーからの入社祝辞があったんですが、その時の言葉は常に意識していますね。若干記憶の改ざんがあるかもしれないですが、
1.拙速は巧緻に勝る
2.まず全部作る
3.自分を個人事業主だと思うこと
と言われまして、今でもずっと守るようにしてます。
トーマツでは新卒の同期が15人ほどいたのですが、基礎知識や能力などで私はビハインドしていて入社後の研修はきつかったですね。その後クライアント配属になったあとも最初の1年は、自分の出来が悪すぎたから思い出したくないのか、仕事の記憶がほとんどありません。2年目の途中からは苦手なことはなるべく手を出さず、得意なプロジェクト全体のストーリー作り、分析、ロジックづくりなどにフォーカスするようになって少しコンサルらしくなった気がします。

-PEファンド投資先とスタートアップベンチャーでのマネジメント経験が有られますがマネジメントを務める際どういった違い、魅力があると感じますか
PEファンドは事業仮説がしっかりしているため遠くにあるゴールを目指すマラソンのような競技、スタートアップベンチャーは日々変わる環境に適応するので短距離走、またはリレー(バトンを渡すのも受け取るのも自分の場合がありますが)のような競技のイメージですね。PEファンドは、事業仮説もイグジットもわかりやすいので達成感を得やすいのと、ファンドのメンバーと壁打ちできるなど、環境面が整っている良さがあります。成果が出しやすい環境が整えられている一方で、時間軸が定められていたり、高いレベルでの論理的・定量的な裏付けを求められたりするので、ポストコンサルの方にとっては普通かもしれませんが、そうでない方にとってはストレスになりうるかもしれません。
スタートアップベンチャーは、何をおいても成長性の高さと、それによる課題の変化への対応力が問われるところが特徴です。これらをしっかり対応していくことによって、自分の考え方や原理原則を会社に浸透させることができるのが魅力かもしれません。創業メンバーにはかないませんが、少なからず自分のDNAのようなものを会社に残していっている実感はありますね。
-ファンド投資先企業を経験されて、現職スタートアップベンチャーを選ばれたご理由と、現職の主な業務内容について確認させてください。
ファンド投資先はちょっと慣れてきたかなという雰囲気も有ったのと、当時周りも結構スタートアップにいく人も多くなってきたので興味を持ちました。またある種スタートアップに行くというよりもキャスターに行きたいという気持ちが強かったかもしれないです。私は石井スポーツ時代にずっとキャスターのサービスを使っておりサービスとしてすごく付加価値が高いと思っていました。シンプルなんですが、生産性を高めるためにしっかりしたサービスだと感じており、ポテンシャルを感じていました。そこで周囲のポストコンサルの友人に、私がスタートアップに行くことについてどう思うか聞いてみたところ全然合っていると思う、という言葉をもらったのが後押しとなって決めました。
入社直後は経営企画室長として、KPI管理の土台づくりと、経営課題の発見と解決をしていました。その後CSO/CFOとして管理本部を管掌するようになって、予算策定・管理、資金調達、人事制度の改正などを行い、上場準備の責任者も務めました。私は上場準備に専門性があるわけではなかったため、方針を定めたり、スムーズに進むようなきっかけを作ったりしただけで、あとはメンバーが責任をもって進めてくれました。2022年からはCSO専任となり海外事業、新規事業、M&Aを担っています。
-現職で上場準備を行う中で、最も困難だったことは何だったのでしょうかまた、どのように乗り越えたのでしょうか。
前述の通り、私が上場準備で果たした役割はさほど大きくはなく、他のメンバー、特に私の後任として管理本部を担ってくれた執行役員陣によって成し遂げられたものだと前置きしたうえでお答えします。
ひとつは、フルリモートワーク企業での上場ということで前例のない論点がいくつも出てしまったことです。例えば、出退勤管理は通常の会社であればタイムカードとドアの開錠履歴を突合することでダブルチェックできますが、リモートワーカーに開錠履歴は当然ありませんから同じプロセスは作れません。結果として、Slackなどを使って解決したのですが、このような論点が継続的に発生しました。
ふたつめは、形式と本質の切り分けです。上場の要件として求められるものは、どれも本質的な目的があると認識しています。しかし、それを業務に落とし込むときには、形式的なルールに置き換えなければいけません。例えば、モノを買うときに購買稟議を通す本質的な理由は、しかるべき責任者が、支払先、目的、支払額を承認することで統制を利かせることにあります。ただ、それをルールに落とし込むと「このワークフローシステムを使って、〇〇部が事前にチェックし、最終的に責任者が承認する」という形式に変わります。すると、「ワークフローシステムが止まってしまったらどうする?」「急ぎの場合に〇〇部の担当がいなかったらどうする?」といった話がでたりします。答えは、「メールなどを使って責任者が承認する」で十分本質的な目的は達成できます。
逆に、責任者が休みなどでいないからと言って、責任者のIDをつかってワークフローに入り別の人が承認してしまったら大問題です。形式的には確かにあってるようにみえますが。このように、本質を理解して、形式にはまらないように議論をコントロールし、そのリズムを作り出すまでは形式に若干振り回されてしまう傾向がありました。
最後は、やはりステークホルダーとの合意形成です。ここは個別具体論点になりすぎてしまうため詳細なお話はしませんが、コンサルやファンド投資先の経験だけでは補完しきれない部分でした。
-2013年~2019年までベインキャピタル、アドバンテッジパートナーズ投資先で勤務されていますがファンドについてはどういった違いがあると感じましたでしょうか。
統計的な違いで分かるほどの数ではないので、私が関与した案件や他の投資先メンバーの話などを総合して回答します(狭い世界なので、元同僚だけでも6人ほどがベイン、アドバンテッジの投資先で勤務しています)。
投資先の企業規模の違いから、PEファンドを通じて採用される経営・マネジメント層の人数が大きく異なりました。念のためお伝えするとPEファンドは、投資したあとで投資先の企業に経営者やマネジメントを新規に採用します。これはよく勘違いされますが、PEファンドに在籍して投資先に出向するのではなく、ほとんどのケースでは投資先に直接雇用されます。そのため、採用プロセスとしてはまずPEファンドで複数回の面談、次に投資先の社長や幹部の方と面談、入社という流れになります。
ベルシステム24では10名以上このようなプロセスで入社されたマネジメント層がいらっしゃったと思います。一方で、石井スポーツでは私を含めて2名(管理サイド1名、事業サイド1名)だけでした。
前者では、施策の実施に際して、ガバナンス面でもプロジェクト推進の慣れの面でも、盤石かつスピーディーに進められる利点があります。もちろんプロパーの方々が変革の主役ではあるものの、このような体制は投資時の初期仮説を徹底して進めるのに適したやり方だったと感じます。
後者では、マネジメント層の大半がプロパー社員となりますので、その方々との合意形成や、施策を推進もその方々が中心になって進めていただく必要がありました。投資時の事業初期仮説も、投資期間中で補正をかけながらすすめましたし、私自身のウィルを反映させる機会が多かったです。またファンド側もかなり業務の細かいところまで入り込んで、現場の人と一緒になって実行していったイメージです。
前者では、ストラクチャーがしっかりしており仮説をしっかり決めてそれに向かって大きいプロジェクトを3~4年走らせるという印象で、後者の方がスタートアップとまでいかないにしても、より流動的だった印象を持ちます。随時確認しながら仮説を変えていくというところでしょうか。
-ファンド投資先で培われた能力はどういったものだったのでしょうか。またもし現職で発揮出来ている点があれば確認させてください
一歩目を作る能力ですね。コンサルのときは、すでにプロジェクトがクライアントからオーダーされているので、プロジェクトを「やる」ということ自体は決まっていて、スマートに組み立てさえできれば、一歩目の苦労はそこまで大きくないんです。むしろプロジェクトをクロージングすることのほうが難しかったりします。一方で、ファンド投資先ではかなりの量のプロジェクトを走らせないといけないが、そもそも「やる」ということに必ずしも社内合意が取れていなかったりします。一歩目を踏み出す前に時間がどんどん過ぎてってしまうんです。私が好んで使う方法は、まずデータを握ってしまう事。例えばキャスターでは基幹システムのアクセス権をくださいと伝え、拾える数字はすべて拾って、なんだったら1か月ぐらいで誰よりも解像度が高い状態にまでもっていく。最初にシステム担当者と仲良くなり、それによってシステム担当者の人がどういうデータを持っているかがわかるようになり、次にそれを使ってプレゼンする感じです。
次に、いったん1人でやってしまってある程度の成果を出してしまうやり方です。例えば石井スポーツでは、CRMの導入に向けた最初の一歩は、1店舗のごくごく一部の顧客を使ってエクセルをベースとした仮想CRMの施策をサンプルで走らせたことでした。顧客の整理、DMのデザイン、ギフト券の準備発送、結果の分析などをすべて行って成果が出ることを検証し、次に5店舗、半年後に全店、そしてそれを仕組み化するためにCRMの導入といったところまで進めました。現職でも同様ですね。まずは経営を見える化するために計数を整理するところから始めたのですが、その土台となるDWHを作って全社計数を出せるようにするところまでは外部協力者と社内のIT担当に手伝ってもらったものの、入社後3-4か月で設計、ツール選定、導入、運営開始までほぼ1人プロジェクトとして完結させました。こういう早さはスタートアップベンチャーでは重宝されますし、小さい成果ではあるものの社内での信頼を得るために私にとっては重要なプロジェクトだったと認識しています。
-川村様の今後の展望についてはどういった事を想定されておりますでしょうか。
あまりキャリアに長期的な展望は持っていません。いまは現職のキャスターで海外事業、新規事業、M&Aの責任を担っていますので、これらが組織的に回るような体制を築き上げることに注力したいと考えています。
-最後にCXO目指されている方・関心を持たれている方にメッセージをお願いします
すみません、インタビューの意図に沿えてないかもしれませんが、CXOという役職自体にあまり意味はないです。象徴的に使っているのだと思いますが、最近は「CXOになりたい、役職がほしい」という方が増えていて違和感を覚えています。ある領域において、誰よりも成果を出すことができれば社内ではCXOの役職がなくてもリーダー・責任者として見られますし、そのような状態になればCXOという役職名を欲しいとも思わなくなります。
では、どうしたら経営レベルで成果が出せるか?という質問に答えるとすると「自分なりの原理原則を持って、それを徹底できるか」ということかと思います。すごく抽象的に聞こえるかもしれませんが、わりと地道・地味な話で、例えば私の場合は、「制度設計をするときは長期的に耐えうる形になっているかどうかを判断基準にする」、「体制づくりはレポートラインをいかにシンプルにするかを重視する」、「業績が良くなったり悪くなったりしたときは、構造的な理由なのか、一過性の理由なのかを切り分けて対応する(つまり一喜一憂しない)」「100点を目指して進まないくらいなら、60点でも前に進んだほうがマシ」などです。これらを持つことによって、瞬間的な判断が可能になりますし、ブレがなくなります。2-3年前に意思決定したことで、すでに記憶にないような話でも、同じ条件を与えられると全く同じプロセスをたどって同じ結論に至ります。
このような原理原則は、一つ一つの事象に真剣に向き合って必ず自分なりのスタンスを持つことでしか醸成できないので、小さい課題や仕事でも適当に判断しないこと、選択肢を出したり報告するだけでなく常にリスクを取って結論を出すスタンスで仕事をすること、など日々の積み重ねかと思います。そのような小さな積み重ねや、自分なりのスタンスがない状態で「とりあえずCXOのポジションが欲しいんです」というのは少し違う気がしています。
無料転職支援サービス
申込フォーム
(目安時間1分)