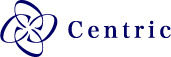プロCFOインタビュー
Professional CFO Interview
PE投資先CFOはいかにビジネスモデル、競争源泉、バリューチェーンを理解し、リアルに利益を極大化させるメカニズムを動かすかが求められる

(元カーライル投資先、現DCapital投資先)株式会社おやつカンパニー
常務執行役員CFO 経営管理本部長
西村裕治様
1990年4月 野崎産業株式会社入社
1999年4月 川鉄商事株式会社(野崎産業との合弁により)入社
2002年3月 株式会社アッカ・ネットワークス入社
2008年7月 株式会社ウィルコム入社(カーライル投資先)
2011年1月 株式会社キトー入社
2017年10月 イチボシ株式会社入社(アドバンテッジパートナーズ投資先)
2019年9月 株式会社おやつカンパニー(カーライル投資先、2022年よりDCapital投資先に)
※インタビュー時(2023年7月時点)での内容となります。
― ご経歴と自己紹介について確認させてください。
企業統合による所属変更を入れると現職まで7社と、一般常識から見ると多い会社歴ですね。業種では商社、通信、メーカーの3種それぞれ約10年ずつ、職種で財務・会計、経営企画、海外事業推進の3種に分けられます。
若手時代から一貫して有しているベース・スキルはファイナンス・アカウンティング領域のものです。ファイナンス関連業務では、商社入社直後の金融商品運用部門への配属がきっかけで、為替のトレーディング等、金融市場取引も経験するなど、一般事業会社では得られない異色の知識と経験を持っていると思います。
その後、ブロードバンド通信ベンチャー、携帯キャリア、産業機械メーカー、食品メーカーでの経営企画に加え、海外事業(東南アジア、カナダ)エグゼキュ―ションを担うことでコーポレート関連業務を超えて事業推進現場での経験を積んできました。
就業ロケーションとしては、商社、メーカー時代に米国、タイ、インドの現地法人に出向。文化、価値観の異なる現地従業員、マネジメントとの事業推進の実績を積んできました。特に彼らのあまり文書化されていないかつ、暗黙の了解になっているようなルールだとか常識だとか、価値観というのをできるだけ早く汲み取っていくという姿勢は、投資先でのマネジメントにも活きている部分があります。
30代半ばに通信業界へ移ってから、PEファンドとのコミュニケーションが始まり、現在に至るまで、色々縁があって今のディ-・キャピタル社傘下の現職に至っています。
それぞれの転職において常に何か自身の新たな可能性を求めていましたが、若かりし頃のそれは、正直、入念に環境を見極め、明確な将来像を描きながらのものではなかったような気がします。
しかしながら、結果としてこれら複数の会社での異なる役割を実地で経験できたことで、幅広い知識と経験を積むことになり、ビジネスパーソンとして差別化されたスキルが構築されたと思っています。
― ご自身の若手時代(20代)で特に印象的だった経験、意識されてきた点はどういった事だったのでしょうか。
振り返ってみると20代の私は、とにかく「仕事ができる人」、「仕事場で充実感を得ている人」という人物像を思い描いていたように思います。人目につかないところで、こっそり書籍を買いあさって自宅(当時は会社の寮)でコツコツ勉強していましたね。 当時の職務であった外国為替取引に関する本を買って学習していました。インターネットもない時代でしたので、書籍が頼り。周囲に専門的な知識を持っている人も少なかったので、今は亡き八重洲ブックセンターへ数知れず通っていました。当時所属していた商社は、仕入の9割近くは輸入という状況でしたので、国際金融取引が事業運営に必須でしたし、この分野の金融理論って結構実際に業務やってない人にとってはとっつきにくい分野でもあるので、若手時代から社内各部門から種々相談が寄せられるようになりました。
商社時代、ほぼ3年周期で転勤等、環境変化があったことも、若手時代にあった重要なイベントであったと思います。商社入社後、東京本社 金融商品部門、大阪支店財務経理部、米国現地法人ニューヨーク本社出向、同社アカウンティング、帰国後、他商社との合併、財務経理部という経緯です。中でも20代でニューヨーク マンハッタンの事務所で働く機会を得たことは当時の私には大きな刺激と仕事に打ち込むモチベーションに繋がりました。
― PEファンドとの出会いはどういったものだったのでしょうか。またどういう点に惹かれ、PE投資先にジョインされたのでしょうか。
最初の出会いは通信ベンチャーに転職した時です。同社の副社長のネットワークに多くの大手金融、ファンドの方がおり、M&Aを含む各種資本政策検討の折、PEファンドとのコミュニケーションが始まりました。
その後、転職検討時にエージェントより紹介された会社が、以前接点のあった大手PEファンドの投資先だったのです。ファンド側の責任者(MD)とも既に面識があったので、とんとん拍子に同社採用となったことが、PEファンドとのかかわりを深くするきっかけとなりました。一方、同社は事業で不調の部分も有り、その際の株主とマネジメントとのコミュニケーションは非常に難しいものだと感じました。案件も大きく、非常にタイトな時間軸の中でのプレッシャーは想像以上でした。
PEファンド傘下企業の営みは、一般事業会社のそれとは大きく異なります。
会社はあくまで投資対象であり、PEファンドは一定期間後、自らの持分を何らかの方法で譲渡し利益を得ることを使命とされた主体です。彼らは投資実行以後、対象会社と様々な取り組みを実践し、対象会社の企業価値を高めることで、自身の利益を獲得するとともに、対象会社のゴーイングコンサーン要件を整え、雇用、取引先、債権者、納税を守ることに繋げています。
この意義深い大事業を進めるためには、資本家の論理だけでは成しえません。誰かが投資家と対象会社の間に立ち、オペレーションの現場を動かしていく必要があります。この役割の一端を担う能力を有するものがPEファンド傘下企業の営みに求められています。そんな一人にたまたま選ばれたということです。

その後、転職検討時にエージェントより紹介された会社が、以前接点のあった大手PEファンドの投資先だったのです。ファンド側の責任者(MD)とも既に面識があったので、とんとん拍子に同社採用となったことが、PEファンドとのかかわりを深くするきっかけとなりました。一方、同社は事業で不調の部分も有り、その際の株主とマネジメントとのコミュニケーションは非常に難しいものだと感じました。案件も大きく、非常にタイトな時間軸の中でのプレッシャーは想像以上でした。
PEファンド傘下企業の営みは、一般事業会社のそれとは大きく異なります。
会社はあくまで投資対象であり、PEファンドは一定期間後、自らの持分を何らかの方法で譲渡し利益を得ることを使命とされた主体です。彼らは投資実行以後、対象会社と様々な取り組みを実践し、対象会社の企業価値を高めることで、自身の利益を獲得するとともに、対象会社のゴーイングコンサーン要件を整え、雇用、取引先、債権者、納税を守ることに繋げています。
この意義深い大事業を進めるためには、資本家の論理だけでは成しえません。誰かが投資家と対象会社の間に立ち、オペレーションの現場を動かしていく必要があります。この役割の一端を担う能力を有するものがPEファンド傘下企業の営みに求められています。そんな一人にたまたま選ばれたということです。

― 現職の業務内容について確認させてください。
常務執行役員CFO 経営管理本部長として、全社経営戦略の立案・推進、重要経営課題のプロジェクト運営等を行っています。業務分掌の垣根は意識せず、やれることはすべて対応するというスタンスで日々の業務を行っています。
あえて具体的な業務内容を上げるとすれば、
■ コーポレート関連では、
・ 年度予算及び中期経営計画の策定、
・ 将来資本政策へ向けた準備(国際会計基準IFRSへの対応準備、財務報告体制強化、社内規程の整備運用、JSOX対応準備)
・ グループ資金計画立案・管理・運営
・ 会計監査計画立案・実行
・ 株主・債権者対応
・ 海外子会社の財務運営サポート、
■ 事業企画に関しては、
・ 過去に会社が行ったことのない事業やプロジェクトの立ち上げ、推進、
・ 機能部門起案施策の評価・企画支援
特に一般的な事業会社のCFO業務と比べてカバー範囲が広いと感じるのは業務プロセスの改善活動ですね。ファンド傘下の企業だと私はメーカーを中心としてきていますが業務プロセス、内部のバリューチェーンの効率化という部分はかなり大きいものがあると感じておりそこに着目しています。業務プロセスがどういった単位で構成されていてそこをどういう人がコントロールしていくかという事を自分で把握する、その上で出てくるアウトプットを数値化、効率化、改善阻害要因は何かという事をメンバーと共有をして成果として出していく。
例えば、前職はイチボシという水産加工業の企業におり、カナダ産のズワイガニを製品化することがその企業の事業モデルでした。その歩留まりというのが非常に重要な指標と捉えており、例えばどういった漁師といつ契約するのか、どのくらいの量を行うのか、それがどういった単価になるのかといった、原料の調達から製品化、在庫の管理までの一貫したバリューチェーンの最適化を行ってきた。その部分の感覚やアプローチ、現場の方々とのコミュニケーションをまず大事にしてきました。そういった部分がファンドが求めるCFOだけではなく、対象企業がマネジメントに求めるところと感じており、ファンドとのコラボレーションが続いている要因ではないかと思っています。
。
― PEファンド投資先での豊富なご経験をされてきておりますが、外資系ファンド、日系ファンド、新興ファンドでどういった違いを感じておりますでしょうか。
外資/日系、新興ファンドという括りで、その違いを類型化することはなかなか難しいのですが、各PEファンドの後ろ盾となっているもの(投資家)が誰なのか、それがどういう意図を持って金主となっているのかは、大枠としてPEファンドの行動を左右すると思います。例えば、投資家の中に公的な立場の人が入っている場合、EXITの方向性というのは比較的定まってくると感じています。日本の産業の育成や産業の活性化を掲げている場合、そこにつながるExitの仕方というのが恐らく求められているのではないかと思うので、そこに向けたマネジメントプレゼンテーションなどを作成します。
しかしながら、同じファンドであったとしても、担当MDとチーム、対象会社の状況(現在のコアコンピテンシーと課題)、エグジット方針(財務ターゲットと持分譲渡方法)によっても接し方が違ってくると思いますので、それぞれの事案がどういう環境の中で取り扱われているのかを俯瞰的に見極める必要があると思います。
私の足元に立ち返れば、現職中にPEファンドが入れ替わるイベントがあったわけですが、当社のバリューアップアプローチに大きな変更はありません。
現在コラボしているディ-・キャピタル社は、メンバーの若さもあり、そのフットワークの良さを活かし、より細かなサポートを提供してくれている印象があります。
― 西村様が多くのファンド投資先でご活躍されてきた秘訣、評価されたポイントはどういった点だったのでしょうか。
対象会社のバリューチェーンとプロセスごとのキーマンに早期にアクセスし、ビジネスモデルの理解に基づくアクションと、そのフォローアップのスピードがファンドの普遍的な価値観にフィットしているということかと思います。プロセスごとのキーマンについては、はじめ部門長とコミュニケーションを取り、その後深堀していく中で出てくるケースが多いです。そうなったら、それ以降直接業務の中で話す人はキーマンの人という形になります。
また、これまでのファンドとのコラボ経験から、投資ファンドとのコミュニケーションに慣れていることもありますね。 一般事業会社 管理部門経験のみの方は、相手がファンドとなると構えてしまい、どのように彼らとの接点を持てばよいのか、会社側マネジメントとのハブとしてどのように振舞えばよいのか等解らずに、適時・適切な情報共有ができないことがあり、意思決定の阻害要因になるケースがあります。
ファンドの意図と背景の理解(どういうレベルのリターンを意図しているのか、そのためのイグジットシナリオはどのようなものか、彼らの投資家とどのようなコミュニケーションがなされているのか等)、事業環境と課題理解力(対象会社のビジネスモデルとバリューチェーンの理解)、課題解決企画力(根本課題の所在とタイムスケールを伴うソリューション企画)、対象会社内及び社外関係者とのコミュニケーション力(社内外関係者との信頼関係の有無)、結果の可視化力(高優先課題とアクション、その期待値とリスク評価等のレポーティング)が必要でしょうね。
― ディー・キャピタルについては「DXxPE」をコンセプトにしており、業界でも注目されているファンドの一つかと思うのですが投資先でやり取りをされてどういった印象を持たれていますか。またディー・キャピタル投資先で働く魅力について確認させてください。
一言でいうと、「構えずフットワークよく働く集団」という印象です。
ディー・キャピタル社内のIT課題対応力に加え、社外のネットワークを活かした企画・提案力があると思います。
現職においては、攻め(ECビジネス等)・守り(製販調整・在庫管理システム刷新等)でのDXニーズがありますが、ディ-・キャピタル社は資本参加当初より積極的に現業部門とコミュニケーションを図り、事業推進をサポートしてくれています。
同ファンドは会社として若いだけでなく、代表以下総じて若い人材で構成されています。これによるファンドとしての機動力は極めて高いものを感じます。前述の現業部門とのコミュニケーションが普通のこととして実施され、レイヤードされていない、フラットなコミュニケーションが進められるチームことが、この機動力を生んでいると思います。
あまり大きな声では言えませんが、時間帯の区別なく発信される私からの照会にも彼らからは速やかにレスが返ってきます。「コロナ禍」を契機に、リモートワークが巷では常識になっていますが、即時レスポンスの有無は、デジタルワークスタイルにおける効率性に密接に関係しており、リモートワークに非効率性を感じる会社はこの部分の欠落(もしくは不十分性)が一因と思いますが、同ファンドとの間には全く問題を感じません。令和日本のビジネスタイルを彼らとは体現できています。

- PE投資先CFOの醍醐味・魅力はどういったものになりますでしょうか。また事業会社CFOとの違いをどのように感じられておりますでしょうか。
期待される役割に大きな違いがあると思います。
一般事業会社におけるCFOも実質的に非常に重要な役割を担っていますが、PEファンド傘下企業のそれに比較すると期待される役割の幅が多少狭くなり、責任範囲がコーポレートイシューに限定される印象を持っています(これは必然であり、どちらが良いというものではありませんが)。
一方、ファンド傘下でのCFOはファンド側の価値観を強く共有・意識し行動することが必要で、より戦略的な意思決定にも参加できるフィールドを与えられている(同時に期待されている)と思います。ここが一般事業会社CFOとの違いであり、醍醐味を感じる根本といっていいと思います。
また、ファンド傘下でのCFOは時間軸が明確にあります。一般的なところで言うと5年程度のスパンでExitを目標にするので、Exitできるような環境を作ります。そういう意味でも、CxO、特にCFOは投資家側から見てより責任・権限が与えられると思います。
PEファンドが投資対象とする企業は、すべからく何等かの競争源泉(コアコンピテンシー)を有していますが、様々な理由によりそれが存分に生かせていない企業です。様々な事業阻害理由を取り除いたり、コアコンピテンシーをさらに活かして成長を図ったりすることがファンドの目的である投資リターンを生むことになります。CFOはその立場を活かし、ファンドの立ち位置からさらに踏み込み、個々のオペレーション、プロジェクトの企画、評価、管理を行っていくことになります。
同環境下での経営推進の視点で持論を交えて言いますと、その方法論検討の段階において、ベストプラクティスと言い、他社の成功事例を持ち込むことに私は賛成の立場ではありません。各社において固有の事情があることを考慮した政策判断が成功確率を上げると私は経験上考えています。そこで会社所属の人間であり、個社のビジネスモデルとバリューチェーンを理解し、ファンドの意向も熟知するCFOが会社とファンドの間に立って政策判断を調整する要として活躍する機会が訪れると考えています。
また、ファンド投資対象会社の多くは中堅企業以下の規模です。つまり、業界には対象会社を上回る規模の競合他社が存在するケースがほとんどですので、その環境下での競争戦略はやはり弱者の戦略になることが多いです。ターゲットセグメンテーションとそれに対するリソースの集中投下が重要で、そのPDCAをいかに高回転で回せるかが投資ファンド傘下企業の成長の決め手となると思います。結果、大企業では成しえない小回りの利いた施策の打ち出しの連続が厳しい環境下での競争を可能にすることと思います。そのような意思決定メカニズムをCFO自らが企画・構築し、推進していくのです。彼らファンドも限られた時間内で成果を出したいので、その迅速なPDCAプロセスには共感し、支援をしてくれるでしょう。会社によっては長年慣れ親しんだ風土や慣習で、実質的な意思決定メカニズムの変革が難しいケースがありますが、PEファンド傘下では、彼らファンドの外的要請等をうまく生かすことで、変革可能な場合が多いと思います。うまくいけば、成果が見えにくい管理部門のプレゼンスが高まり、メンバーのやる気を引き出していくことにもつながっていくと思います。
更にPEファンドとの取り組みの後に残るもので最も大きなものは会社経営としての感性とノウハウといっても過言ではないと思います。もちろん、CEOのように幅広い業界ネットワークと業界知識を持って全社を牽引する担い手ではありませんが、会社をどのように運営していけばよいのか、CEOをどのように補佐し、その他のステークホルダーとの関係を維持し、会社を運営していけばよいかという総合的な経営者能力を比較的早期に獲得できるのではないかと思います。上場大企業ではおそらくこのような結果を得ることは容易ではないでしょう。投資対象会社にはビジョンはあるか、短期の目標の積み重ね、重ね設備投資やブランド投資を行う。結局やりたい人にはやらせていきたい。
- PE投資先では勤務を開始される際にどういった事からスタートされるのでしょうか。
会社文化やルール等を身に着けるという意味で、投資先の経営陣・社員との関係構築、はもちろん同時にこちらから働きかける事も行います。特にファンドの方々とのコミュニケーションは最初からロケットスタートです。そこに何も配慮もいらないので、最初の頃からリアルな方向性、課題認識を共有するようにします。また私の希望もできる限り早くから伝えるようにします。ファンドの方々は何の配慮もなくできる人達だと考えています。
- PE投資先のCFOはファンド側と投資先とのコミュニケーションハブになる事もあると思いますが、その際西村さんはどういった事を心がけているのでしょうか。
長期的なビジョンというのはあると思うんですけれども、その長期的なターゲットに対してどのように今やるかっていうことについては、むしろその短期の戦略の積み重ねによってしかそれはできないと思っています。それで言うと、ファンド側の持つ意向とそれに沿ったプランっていうのは、実はそんなに相いれないものじゃないっていうふうに思っていますのでそういうその視野に立って、戦略を立てて、コミュニケーションをします。
- PE投資先CFOを務められて特に苦労された点はどういった事だったのでしょうか。またどのようにそれを乗り越えられたのでしょうか。
PEファンドとのコラボを始めた当初(通信ベンチャー時代)は、対象会社の現場責任者との信頼関係構築に苦労しました。やはり事業はオペレーションの現場で実行されていますから、いくらファイナンス理論や管理会計で事業の実態を可視化できたところで、オペレーションの現場を押さえないと(ビジネスモデルと社内バリューチェーンの理解とそれを司るキーマンとの信頼関係構築)、自身の主張に説得力がないなと感じていました。そこで、オペレーション現場のキーマン(必ずしも担当役員とは限らない)を見つけ出し、その人とのコミュニケーションを密にし、信頼関係を構築することで、事業計画にも説得力を持たせることができるようになりましたし、結果として現業部門担当役員との信頼関係にもつながっていきました。
各機能部門との関係構築の方法論としては、各部門によるマネジメント報告や、ルーチンワーク以外のプロジェクト推進支援が取っ掛かりとしては良いでしょう。
具体的には各部門ごとのミッションを私ならではの視点でバックアップするという形です。部門の人たちがマネジメントや株主に向かって話すという事をサポートする形にし、彼らの成果としてできるもしくはモチベーションに繋がるような形でサポートすることにより関係構築できると感じています。これにより部門長のみならず、現場のキーマンとの関係も構築でき、かつCFO自身の自社バリューチェーンの理解が深まり、自身の戦略立案能力の強化につながります。このアプローチにはそれなりの自身のワークロードを割かなくてはならず、体力消耗が伴いますが、根気よく実施することで、確実に仕事の成果につながっていきます。
-西村様の今後の展望についてはどういった事を考えておりますでしょうか。
今年の1月の株主交代イベントで、PEファンドとのコラボによる私のCFO業ノウハウは完成された感覚を持っています。
対象会社固有のビジネスモデル、バリューチェーン把握、それを活かした中期的企業価値向上計画の立案・実行・管理、トレードセール・株式公開等のイグジットシナリオの立案と実行、ファンドイグジット後の新体制移行手続きといった一貫したプロセスを遂行するための知識と経験が複数ファンド傘下企業での経験によって自信をもって遂行できる状況になったということですね。私のこのスキルはメーカー案件で成果を最大化するものと理解しています。
足元に立ち返ると、ディ-・キャピタル社とのコラボレーションが始まったばかり。まずはこの会社を彼らとどのようにバリューアップさせていくかが私の頭の中の大部分を占めています。環境変化に、臨機応変に対応できる準備を整えつつ、目の前のミッションを確実にこなしていきたいですね。それが私自身の存在価値の向上にもつながると思っています。
-最後にPE投資先CFO目指されている方・関心を持たれている方にメッセージをお願いします。
PEファンド傘下企業CFOの役割は、その対象企業により様々ですが、先ず言えることは、このポジションは単なる財務・会計のスペシャリストでは十分な成果は出せないということです。
いかにビジネスモデル、競争源泉、バリューチェーンを理解し、リアルに利益を極大化させるメカニズムを動かすかが求められることとなります。
そのための労力を惜しまずやって、成果を出せたとき、きっと自立心の高い皆さんはこの上ない充実感を味合うことになるでしょう。自立心が強く、コーポレート分野で強い強みを持ちつつも、所属組織の文化・風土、そのほか様々なしがらみで十分に能力を発揮できていないと思われる方は、PEファンドとのコラボレーションを一考してみてはいかがでしょうか。この分野の経験を積むことで、その後のご自身のブランド価値は確実に高まり、選択肢も広がってくることでしょう。
最後に、メンタル・フィジカルのタフさを求められるポジションでもありますので、是非、普段の生活でのセルフコントロールを心掛け、心身ともに健全な状態でご自身の目標に向け進んでもらいたいと思います。

無料転職支援サービス
申込フォーム
(目安時間1分)