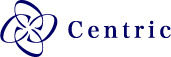プロCFOインタビュー
Professional CFO Interview
大企業からファンド投資先CFOへ ― 経営変革の最前線に立ち続ける理由

株式会社KMCT
CFO
滝 兼市様
≪経歴≫
1996年04月 株式会社資生堂
2023年05月 株式会社KMCT
(2022年3月に丸の内キャピタルと資本提携)
-ご経歴と自己紹介について確認させてください。
1996年に㈱資生堂に入社し、約20年間、財務・経理領域を中心にキャリアを積みました。単体・連結決算、管理会計、中期経営計画策定、M&Aなど幅広い業務を担当。2016年からは中国に駐在し、現地法人の経営管理やロジスティクス改革を推進し、利益率を改善し、特に物流費は数億円規模で削減しました。2023年からはKMCTのCFOとして、製造業×ファンドの環境で基盤整備と変革を進めています。
-ご自身の若手時代(20代)で特に印象的だった経験、意識されてきた点はどういった事だったのでしょうか。
社会人としてのスタートは「会計ビッグバン」の時代でした。日本の会計制度が単体主義から連結主義へと大きく転換する最前線で制度対応に追われ、昼夜を問わず学び続けました。その中で「自ら学び、変化に適応する力」の大切さを痛感し、この姿勢は海外での業務や経営管理、そしてファンドCFOとしての挑戦にも生きています。
-資生堂中国での大規模な組織改革・収益性改善を短期間で成し遂げた際、どのような意思決定プロセスとマネジメントを実践されたのでしょうか?
中国駐在時はSCM全体も管掌し、見直しの中で主要3PLの入れ替えを含む物流改革を進めました。入札プロセスの透明化、KPIの再設計、SLA(合意されたサービス水準)の明確化を行い、誤配送を減らし、物流費を圧縮しました。ファイナンスの観点から改革のヒントを得つつも、実行には横断的なノウハウと現場を動かす力が不可欠です。両面を意識し、現地メンバーやパートナーと課題を共有して解決策を探り、メンバーが「自分たちの未来をつくる」と感じる意識変化が生まれました。こうした経験は、ファンド投資先でも求められる「チームで変革を進める」感覚につながっています。
-中国駐在で最も難しかった意思決定はありましたか。
多々ありました。例えば、当時の北京会社は前職の会社が65%、北京市が35%を保有する合弁で、その運営には苦労しました。また、中国内に21あった分公司を縮小・統合する判断を下し、実行した局面です。顔の見える部下や関係者に対して下す判断は重いものでした。また、一部機能の上海移転でも同様に難しい判断の連続でした。会社としては「公平性・法令順守・人への配慮」を原則に、①事前説明 ②選択可能な配置転換 ③再就職支援 ④補償基準の透明化 を進めましたが、歴史ある会社ゆえ愛着も強く、実質的に職を失うと受け止められる場面もあり、直接のクレームや涙ながらの訴えにも向き合いました。
物流再編では、自社だけでなく、従前の3PL会社の社員が、当社の決断により閉鎖・解雇に至るケースも経験しました。顔が見えるからこそ難しい判断が多く、しがらみや過去の積み重ねをゼロ、あるいはプラスに切り替える判断と実践には、重い責任を感じました。
-資生堂時代から継続して取り組まれているM&Aやアライアンスにおいて、特に気を付けているポイントはありますか。
M&Aやアライアンスの成否は、「思惑の一致」をどこまで構造化できるかにかかっています。特に、自社のメリットだけでなく、相手に寄り添い、相手にとってのメリットをどう最大化するかという視点を大切にしています。EXITの先を見据え、ステークホルダーにとってのプラスとは何かを常に意識しています。
先日、九州への出張で、前職時代(約10年前)に売却をリードしたブランドが、現在もきちんと展開されているのを偶然目にし、10年後も輝き続ける姿に非常にうれしく感じました。
-逆にこれはうまくいかなかったというケースはありますか。また、その際に得られた教訓もありましたら確認させてください。
先方の期待値に合致しなかったり、競合の提案が勝ったことで、ディールに至らなかった案件もあります。M&Aを実現するには、シナジーや相手の期待値を最大化できなければ結果につながりません。また、売却では、新しいオーナーのもとで企業やブランドがさらに良くなるビジョンが見え、それが伝わると判断できる場合には、新たな株主・資本の方が望ましいと感じます。結局、今ではなく5年先・10年先を見据えたとき、うまくいっている確信を持てるかが分かれ目です。
-資生堂での20年以上のキャリアを経て、製造業かつファンド傘下企業であるKMCTのCFOに就任された背景と、その際にご自身の役割をどう定義されたかをお聞かせください。
前職を通じてファンド投資先経営に関心を持ち、エージェントの紹介をきっかけに現職に就きました。ファンド投資先についての印象は、入る前後で大きく変わっていません。大企業のCFOは経理・財務が中心ですが、ファンド投資先のCFOはバックオフィス全般が求められます。業務範囲は広く、一定の専門知識と経験が必要です。ファイナンスだけに強いだけでは足りず、人事・IT・法務の知見も不可欠で、自身のノウハウやキャリアを生かせると考えました。
また、ファンドからは「投資家」と「事業会社」の間に立ち、双方の価値観を調整し全体最適を導く役割を期待されています。事業会社CFOの経験を基盤に、より広範でスピード感ある変革を仲間とともに推進しています。
-資生堂でのどのような経験が活きていると感じていますか。
多面的な知識と経験が生きていると感じます。例えば、法務ではビジネス法務の知識、HRでは労働法の知識というように総合的な知見が必要になります。
また、今回はカーブアウト案件のため、まず従来制度の今日的な過不足を見直し、必要に応じて再設計しています。その中でも、従前のノウハウが生きていると感じます。さらに、日本だけでなく海外にも子会社があるため、実行に至らない場合でも、検討段階から国内外の構造改革や労働法対応の経験・知見が活用されています。
-ファンドの方々と現場の間に入っている中で、難しい局面やハレーションのようなものはありましたか。また立ち回りとして工夫していたことなどありましたら教えて下さい
ハレーションとまでは言いませんが、カルチャーの違いはあります。ファンドの考え方が従前の会社カルチャーと異なる点は、ファンド側も理解しています。会社側でも、環境が変われば考え方も変わっていくという認識が浸透しつつあります。したがって、どちらが正しいかではなく、双方の翻訳者としての役割が期待されています。金融業界と事業会社の共通言語をブリッジすることも、私の重要な役割だと認識しています。
-ファンドとはどのくらいの頻度でレポーティングされているのでしょうか。
週1回の定例で全体を確認し、重要な論点は随時、必要な深さで議論します。ファンドメンバーや社長と一緒にアップデートする形で進めています。
-KMCTにおける「バックオフィス機能の再構築」で、最も困難だった点と、それをどう乗り越えたかを教えてください。
KMCTは、異なる文化や業務フローを持つ3社の再編企業です。大手のカーブアウト案件でもあり、独立した企業体としてバックオフィス機能を強化・構築することが急務です。例えばシステムは、スタンドアロン化を目指して構築中です。
取り組みでは、現場メンバーの意見を吸い上げ、現場自ら変えていくことを促しながら、最適解を一緒に作る進め方を重視しています。同じ視点を持つメンバーがいる点にも助けられています。
また、必要な人材を外部から積極的に集め、将来のための制度や仕組みを整えることが重要だと考えています。これらが、将来を見据えた自走できる組織の土台になります。採用面では、日本では「知名度のある大企業」を志向する方が多い現実があり、旧親会社のブランドに頼れない中で人材を採用するのは容易ではありません。バックオフィスに限らない全社的な課題であり、「選ばれる会社」になることの難易度は高いと感じています。これは当社に限らず、多くの企業が直面している課題だと思います。
-CFOとして、ビジネスモデル変革において「財務の視点から最も重要」と考える観点は何でしょうか?
収益性をどう定義し、可視化して事業判断に生かすかが重要です。特にファンド投資先では、資本効率やキャッシュ創出力を重視したKPI設計を進めています。財務部門は数字の番人に留まらず、事業と並走し、社長やファンドが実現したい変革を支える「経営のブレーン」としての役割が重要です。
-CFOの職責の中で、単なる数字管理を超えて“事業成長のドライバー”になるために意識していることはありますか?
財務視点だけに閉じず、「人と組織」をどう動かすかに注力しています。戦略を実行するには、適切な人材要件や組織体制が不可欠です。CFOとして経営メンバーを巻き込み、仲間とともに組織を変えていくことに日々取り組んでいます。
-CFOとしてこれは難しかったと思う意思決定や経験はありますか。
ファンド投資先は、時間軸の面で事業会社より難易度が高いと感じています。ファンドは限られた時間の中でリターンが重視されるため、投資リターンと時間(IRR)が重要な物差しになります。制約の中で結果を出すには、優先順位と順番で成果を積み上げていくことが求められます。ファンドの方々も事業に寄り添い、現実的な落としどころを一緒に探す関係が構築できており、助かっています。
-大企業とファンド投資先企業において、それぞれの働き方の違いや魅力はどのように感じられていますか?
最大の違いは「時間軸」と「役割の広さ」です。ファンド投資先では、CFOは財務にとどまらずHR・IT・法務も束ねます。事業会社CFOも重要ですが、ファンドCFOはより多面的で高度な挑戦が求められ、その分、成長の機会も大きいと実感しています。
-ご自身の思う、ファンド投資先CFOとして必要なスキルセットとマインドセットについて確認させて下さい。
ファンドCFOには、ファイナンスに加え、HR・IT・法務など管理全般を束ねる広い視野が必要です。旧親会社のインフラやノウハウに頼らず、ゼロから組織をつくり変えていくうえで、人事・総務などの経験も重要です。加えて、事業会社以上に素早い判断と多様な経験、変革の痛みを引き受ける胆力が求められます。
-滝さんがファンド側の人間でしたら、投資先にどのような人材を採用したいですか。
投資先のステージによって、採用すべき人材像は変わります。カーブアウトのように規模や人材がある程度そろっている場合は、ファイナンスに強みを持ちつつ、総合的な経験を持つ人材が軸です。一方、未整備なスタートアップのような案件では、ハンズオンで動けて、自走できる仕組みを残せる人材が必要です。仕組みを残せないと、後々、組織が回らなくなることがあるためです。
-最後に、今後ファンド投資先CFOを目指されている方へ何かメッセージをお願い致します。
ファンドCFOは、非常に高い難易度と責任を伴う役割です。その分、企業変革の最前線で経営に深く関わり、自身の成長も加速しています。財務の枠を超え、仲間と会社を良くしていく経験は、キャリアの中でも得難い財産になっています。
無料転職支援サービス
申込フォーム
(目安時間1分)