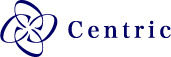プロCFOインタビュー
Professional CFO Interview
小さくてもいいのでクイックウィンを作ることで、 現場の信頼感を得ることが出来る
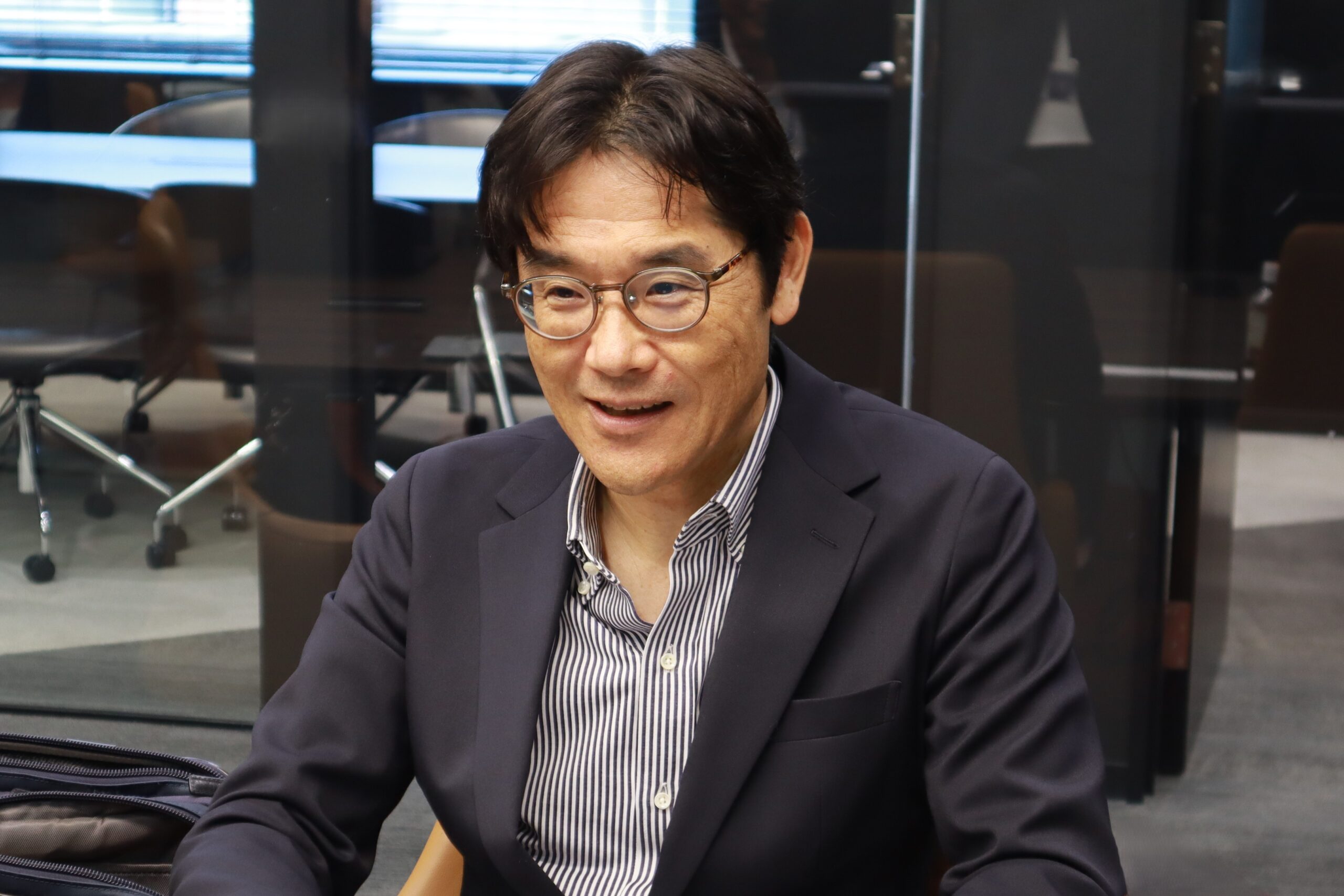
リライフメンテホールディングス株式会社
代表取締役CFO
山本 融様
1991年04月 日商岩井株式会社
2002年10月 株式会社リサ・パートナーズ
2003年10月 イノベーションエンジン株式会社
2004年05月 株式会社リンクセオリーホールディングス
2006年10月 ラオックス株式会社(執行役員管理本部長)
(2004年11月にMKSパートナーズと資本提携)
2008年02月 リアルコム株式会社(取締役CFO)
2013年01月 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
(2016年4月に子会社Jurlique International CEO就任)
2023年07月 株式会社山本水産輸送(取締役CFO)
(2023年5月に農林中金キャピタルと資本提携)
2024年07月 リライフメンテホールディングス株式会社(代表取締役CFO)
(2023年9月にJGIAと資本提携)
-ご経歴と自己紹介について確認させてください。
1991年に新卒で大手総合商社(日商岩井)に入社後、主に下記の経歴を歩んできました。うち約14年は海外の現地子会社のマネジメントを経験しています。(商社インドネシア子会社、日系化粧品グループ豪州買収先)。
その後、直近2社でPEファンド投資先にてCFOを経験しています。
・大手家電量販店(執行役員管理本部長)
・上場ソフトウェア開発(取締役CFO)
・日系化粧品グループ豪州買収先化粧品会社(CEO)
・PEファンド投資先運送業(取締役CFO)
・PEファンド投資先インフラ事業(代表取締役CFO)
-ご自身の若手時代(20代)で特に印象的だった経験、意識されてきた点はどういった事だったのでしょうか。
何となくというレベルでしたが、海外で仕事をしてみたいという思いが学生時代からあり、商社(日商岩井、現双日)に入社できたことは嬉しかったです。実際に、入社7年目にインドネシア・ジャカルタでの海外駐在の経験が現在のキャリアのベースになっていると思っています。当時、私自身は29歳になりたてでした。また、当時は駐在事務所ではなくいわゆる事業会社に入り込みました。駐在先は、車部門の子会社で現地財閥系の会社と、車のオートリース事業を行っている会社を立ち上げた合弁会社で、自動車部門から社長が来て、オートリース事業から副社長が来て、管理部門の責任者として私が就任し、それ以外は全員インドネシア人という中で仕事をしました。バスを差し押さえに行ったりだとか、言葉の問題があったりだとか、その時の経験は色々とあるのですが、当時の経験がCFOを目指したいという、出発点になっています。
そのあと日本に帰って数年後に、ファンド傘下のラオックスにジョインすることになりますが、当時再生ファンドの時代で、そこでCFOを務められる方は戦略コンサル出身や海外MBAを取得している方が多く活躍していました。私はそういった経験はありませんでしたが、やはり商社での駐在経験があったからこそ頂けた機会でしたので、ジャカルタが私にとっての出発点だと今でも思っています。
-当時再生ファンド傘下のラオックスやポーラ・オルビスなど、大手企業での経営再建や成長戦略に関わられたご経験について、特に印象的だったプロジェクトを教えてください。
ラオックスでは、初めてのファンド投資先での経験でした。同社は歴史もあり、家電量販店という領域では、いわゆる老舗で、ラオックスというブランドは確立されていた一方で、戦略構築力やオペレーション遂行力、組織風土など多くの問題を抱えており、事業再生というフェーズでした。上場を維持しながら、1,000億円近い売上規模をもった事業体の資金繰り管理やレンダーとのやりとり等などに追われる状況で、いわゆる会社の変革をもたらすという大胆かつ地道な取り組みができる環境ではなかったと、今振り返るとそう思います。そういう環境下でもなんとか会社を存続させることが出来たのは自分自身にとっては貴重な経験でした。
2013年に入社したポーラ・オルビスでは主に買収した海外ブランドの支援に携わりました。2014年にはそのうちの一つであるジュリークに出向をさせていただくことになるわけですが、やはり日本企業と仕事の進め方が違うなというのは強く感じました。海外(欧米的な)では個人個人の専門性や経験がより全面的に出ており、一方、伝統的な日本企業では新卒で入ってその会社のカルチャーの中で育った人材の集合体が組織として物事を進めていくという形であり、どちらが良い悪いという話ではないと思いますが、双方の良いところを上手く融合できないかなと思いました。
-海外ブランド(Jurlique International)のCEOとしてグローバルマネジメントを経験された中で、日本企業と海外企業での経営スタイルの違いをどう感じられましたか?また、そこで得られたことや苦労した点について確認させて下さい。
オーストラリアのブランドでマネジメントの経験をさせていただいたのですが、チームメンバーはオーストラリア人、イギリス人、フランス人、ニュージーランド人、中国人、日本からの出向者など、多岐にわっていました。主要マーケットも本国であるオーストラリアだけでなく、中国、香港、免税、日本、アメリカなどで事業展開をしており、各市場での動向も違い、マーケティングや営業などの考え方も各市場で異なるなど、ダイナミックである反面、マネジメントは苦労しました。又、製品の製造プロセスや品質への考え方も日本とは違いました。自分自身としては、多様性の中でマネジメントをする経験の中で、積極的に自分の考えを組織全体に発信したり、各メンバーとコミュニケーションしたりということを心がけていました。個々のメンバーは専門性も高く、各人ともに自分のテリトリーにおいて自分のスタイルを強く出そうという傾向が強く、上司である私にも遠慮なく自分の考えを伝えてきました。その中で、全体感を持って、優先順位を付けて事業運営をしていかなければならないので、各マネジメントのメンバーとは、こちらも遠慮なく話をするようにしました。この様な経験は今の自分のマネジメントスタイルにも出ているのではと思っています。
-私との初回面談の際も、ジュリークでの経験が印象的で、これまでの人生の中でコアな経験と言われていましたね。
まさにその通りで、再度海外に行けたということは幸運だったと思いますし、理由はいくつかありますが、社長をやらせてもらったという経験は貴重でした。ジュリークは、日本でも百貨店で売っていたりするので知っている人は知っている歴史ある老舗ブランドですが、チーム全員外国人という中で、外国人メンバーを束ねていくタフさというところは一段上がったなという経験になったと思います。あとは製造業を経験したことが無かったので、品質管理とか安全面、また工場をどのように効率良く回していくかというトータルでバリューチェーンが見ることが出来たというのは自分自身の経験の幅が広がったなと思います。
-これまで複数の企業で経営に携わってこられましたが、キャリアの節目でどのような判断軸をお持ちでしたか?また、「これは転機だった」と感じる出来事があれば教えてください。
先にも述べましたが、日商岩井時代のインドネシアでの子会社駐在の経験がCFOを目指して行きたいと思うきっかけになりました。また、ジュリークではCEOをやらせていただく機会もあり、本当の意味で会社の経営やリーダーシップを発揮する経験ができたのではと思っています。
-山本水産時代のCFOとしてのミッションとして、主に複数のグループ会社PMIを行う上で、特に意識していたポイントや心がけていたことがあれば確認させて下さい。
短期間の投資期間の中で、事業や数値管理の仕組み作りを会社の勢いを削がずに構築するべきかを考えさせられる機会となりました。
単に、「ここが出来ていないからこういうプロジェクトを立てて、こういうところを見える化していきましょう」だけでは現場から反発を受けることもあります。ですから、10個プロジェクトを立てて、少しずつ改善していくというよりは、まずはベーシックなところを1個か2個やってみることが大事だと思います。また、1回ではうまく行かないということを前提に、2回目、3回目をやっていくと、お互いに共通の認識が出来てきて、それでは次もやってみましょうかとなっていくと思います。
-JGIA投資先リライフメンテホールディングス(株)を選ばれた理由について確認させて下さい。
インフラ老朽化の進行、現場を支える人手不足、中小事業者の事業承継という建設業(社会インフラメンテナンス事業)を取り巻く環境に対して、個社個社では事業成長や継続が難しく、結果日本全体の問題として未来を支える社会インフラが立ち行かなくなる、という大きな課題にチャレンジできるというところが一番の決め手となりました。インフラメンテナンス事業者の受け皿となるグループ形成やホールディングスの機能の充実というところにマネジメントとして関われるというところも魅力でした。よくある経営管理のみならず、M&Aの継続的な推進と型化、人材採用支援、ブランディングなど、事業成長に挑戦できるというのはCEOでの経験が生きるのではないかと考えました。
-ジョインした際、まず最初に何を行いましたか?
何もないところからだったということもあり、体制作りを行うという機会が目の前にありましたので、タイミングとしては非常に良かったなと感じています。その中で、なかなか数字を月次で把握することがうまくいっていなかったところを整えていったり、ファンドとのやり取りの中で会議体を立ち上げて回していくということもやりました。あとは人事制度を変えてみたりということも行いました。
-現在は主にどんな業務を行っていますか?
ホールディングスの代表取締役CFOとして、M&A推進を軸に、ホールディングスの組織作り、機能構築、改善を行っています。
-ファンドとのレポーティングはどのくらいの頻度でどのようなやり取りをされているのでしょうか。
今は毎週行っています。担当者もハンズオンして頂いているので、また、比率的にいうとうちの案件に重きを置いてくれているようなので、いわゆる非公式な経営会議を毎週行ったりだとか、私とも個別に毎週行ったり、チャットとかではほぼ毎日やり取りをしています。
-資本提携(MKSパートナーズ、農林中金キャピタル、JGIAなど)を通じて感じた、企業
成長と株主との関係性についてお考えをお聞かせください。
また、各ファンドの印象や違いがあれば確認させて下さい。
投資ファンドといってもそれぞれの理念や投資基準も違うので、一概には言えないですが、どこかのタイミングでExitするので、Exitを最大化するという意味では同じ船にのっているという認識を持つべきだと思います。その上で、Exit後の会社の基盤作りもあわせて行っっていくというバランスが大事だと考えます。JGIAは長期目線を持って、会社のマネジメントと対峙してくれており、非常に健全な議論ができていると感じています。このあたりはファンドによっても考え方が異なってくると思っていて、今回JGIAとお仕事できているのは非常にラッキーだったなと感じています。
-ファンドとの相性も凄く大事だと思いますが、事前に見極める方法はありますか?
一度も経験していないとなかなか難しい部分はあります。ファンド傘下でやろうと決めたのであれば、1回は失敗するのを覚悟するぐらいの気持ちは必要だと思います。仮に1回目は上手くいかなかったとしても、2回目は免疫がついているので・・・。スキルや能力とかではないと思っていて、決めたらやり切るというタフさがあればいけるのだと私は思っています。
-大企業とファンド投資先企業において、それぞれの働き方の違いや魅力はどのように感じられていますか?
大企業でもファンドでも基本変わらないと思います。どちらにいてもどの様な仕事をするかというところが重要だと考えます。だだ、大企業は部門によっては変化が少なく、安定している分、エキサイティングではないかと感じます。
-ご自身の思う、ファンド投資先CFOとして必要なスキルセットとマインドセットについて確認させて下さい。
基本的には、外から来た人という見られ方をされるので、「ここを改善しました」みたいな小さくてもいいのでそういったクイックウィンが必要だと感じています。現場から信頼感を得ることができるかというのはその後の成否にとって大事だと思います。コミュニケーション能力、バランス感覚をベースとしながらも、会社をどの様に変革していくのかというメッセージを伝えることも必要だと思います。
また、ベタですが会社の状況を数字で見ることができ、その状況を自分なりに理解する能力は必要です。
-山本さんがファンド側の立場でしたら、どんなCFOの方にジョインしてもらいたいですか?
財務経理など数値だけに強いというだけでは不十分だと思います。やっぱりバランスが良い人が良いと思います。例えば、頭でっかち過ぎるとなかなか現場に受け入れてもらうのも難しいですし、相手がどういう認識レベルなのか、同じことを言うのでも、ちゃんと斟酌してしっかりと話ができて、こちらが期待しているものを引き出すというところが大事かと思います。自分の言いたいことを言って、それ自体は間違っていなくても、通じてないじゃないですかってことが多いのです。言いたいことを言うだけではだめだとはちょっと思います。
-最後に、今後ファンド投資先を目指されている方へ何かメッセージをお願い致します。
非常にチャレンジングな環境ではありますが、自分を大きく成長させることができる良い機会でもあります。1回の失敗でくじけることなく、果敢に挑戦してほしいと思います。
無料転職支援サービス
申込フォーム
(目安時間1分)