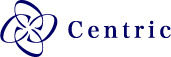プロCFOへの道~スタートアップ編~
Professional CFO Column
Profile

大学卒業後、投資銀行でM&Aアドバイザリーを経験後、日系PEファンドにて投資のソーシング、エグゼキューション、その後の投資先の経営支援、ファンドレイズにも一部関与。
その後著名スタートアップCFOとして、主にコーポレート部門を統括し、大型資金調達を実現。
プロCFOへの道
~スタートアップ編~
スタートアップのCFOに興味・関心のある読者の皆様に対して、投資銀行・PEファンド出身で、スタートアップのCFOを務めてきた筆者が経験したものを少しでも還元できるように、皆様が興味を持って頂けそうなトピックを選定し、コラムを書きました。全6回を予定していますので、宜しくお願い致します。
― 1. スタートアップCFOの主な採用ルート
スタートアップと一括りでいっても、シード→アーリー→ミドル→レイター(→上場)などといったような形で、従業員規模や事業の状況によって、いくつかのステージに区分されます。シードやアーリーの段階では、CFOのメイン業務である資金調達を社長が担っているケースが多く、かつ、CFOの高い報酬水準も勘案し、この段階ではCFOの採用を行っている企業はそこまで多い訳ではありません(但し、最近ではアーリー段階から海外投資家も含めて大型調達を行っているケースもあり、そのようなケースでは早い段階でCFO採用に動いているスタートアップも存在します)。
一方で、ミドルやレイターステージになってくると、海外投資家も含めた大型調達をするケースが増えてくるのと、IPOに向けた準備が本格的に始まるため、CFOの採用に動き始めます。主な採用ルートは、以下の通りとなります。
①エージェント経由
スタートアップに限らず、通常の採用と同様、採用エージェントからの紹介で、スタートアップに転職するルートになります。スタートアップ企業のCFOを志すうえで、その企業のビジネスモデルや今後の成長性、業界のポジショニングなどといった要素は当然重要である一方、社長との相性や社内のカルチャー・雰囲気などといった要素も極めて重要となることから、エージェント経由でそういった情報収集を行うのは有効な手段となります。
②VC経由
CFO人材の場合、報酬が他職種と比較しても高い傾向にあることから、スタートアップサイドからすると、できるだけ採用コストを抑えた形で採用したいところであります。そこで、当該スタートアップに出資しているVCも一緒になって、CFOを含めたハイレイヤー採用をサポートしてくれるケースも少なくはありません。
VCサイドからしても、投資先の採用コストを抑えられるだけでなく、優秀なCFOを採用することで、投資先の事業成長の加速やその後の円滑な資金調達、Exit時の価値最大化といった様々な観点で、採用をサポートすることの合理性が高いと言えます。
VC各社でもCxO人材の採用プールを強化しており、例えばCoral CapitalやALL STAR SAAS FUNDなどは、彼らのキャリアサイトに登録すると、彼らの投資先から直接アプローチが来たり、スタートアップに関する各種イベントの案内があったりと、情報収集をするには有益な内容となっています。
③ビズリーチやリンクトインによるスカウトメール
スタートアップによっては、経営陣が自ら文章を作成し、それぞれの採用候補者の属性に応じて中身を変えながらスカウトメールを真剣に送っているケースもあります。スタートアップサイドからすると、エージェント経由での採用と比して採用コストが抑えられるだけでなく、待ちの姿勢ではアプローチしきれない層にコンタクトできることから、大半の会社が活用している印象です。
④直接応募・リファラル
意外と多いのが、投資銀行などでスタートアップ企業を担当しており、その企業の成長性や経営者との相性を把握してから転職するケースになります。再現性は高くないものの、その企業の実態をより正確に把握できることから、有力な採用ルートとなることがあります。
― 2. 選考プロセス
通常、スタートアップCFOの選考においては、1) 創業者CEOとの面談、2) 他経営メンバーとの面談、3) 主要株主との面談、などを行うのが通常のプロセスとなっています。また面談形式だけでなく、CxOなどのハイレイヤーポジションにおいては、2名程度のレファレンスチェックを実施する企業も増えてきています。
スタートアップサイドの見極めポイントとしては、CFOとしてのファイナンス関連の知識や経験を評価するだけでなく、創業オーナーを中心とした企業カルチャーとのフィット感を特に注視して評価を行っています。
選考プロセスに臨むにあたっては、当該スタートアップのビジネスモデルや取り巻く環境を事前に入念にリサーチし、一定の成長仮説などを持ちつつ、面談プロセスでの質疑応答を通じて、さらにブラッシュアップしながら解像度を高めていくことが重要となります。筆者自身も、(自腹で)ビザスク経由で応募している企業の競合企業の方へのインタビューを実施し、解像度を高めたうえで、自身がCFOであればどういったエクイティストーリーを構築し、IPOを目指していくかなどについて、面談の場で説明を行っていきました。
― 3. CFOの実際の業務内容・求められる経験やスキル
一般的にはスタートアップ企業のCFOが行う業務内容として、
●資金調達(国内外の投資家からのエクイティ及びデットによる調達)
●経営管理と(株主や金融機関向け)レポーティング
●バックオフィスの強化・IPO準備
●資本政策の立案及び実行
●事業計画・事業/組織戦略の策定・モニタリング・実行
●M&A(ソーシング~エグゼキューション~PMI)
などが挙げられ、これらに付随するスキルや経験は必須要件として求められます。
それに加えて、常に様々なリソース不足と戦うスタートアップ企業においては、「足りないものは全て自分で対応する」くらいの意気込みと業務の染み出しが行われるケースが大半であります。企業や人によって様々ではありますが、自社製品の営業を大企業向けにする人もいれば、プロダクトチームを兼務する人もいます。こういったことが起こるのは当たり前だし、むしろウェルカムくらいのマインドセットを持った人材が、スタートアップCFOとして相性が高いと言えます。
その他、企業経営を行っていくうえでは、種々雑多なトラブルに対応し続ける必要があります。特に従業員規模が数十人から数百人と大きくなっていくフェーズにおいては、組織マネジメントに割く時間も増えていくことになり、時として強い忍耐力・胆力も求められます。
最後に、これは100%必須という訳ではありませんが、英語によるコミュニケーションについては、できるに越したことはないかと思います。特に大型の資金調達やその後のIPOも見据えると、海外の投資家と直接やりとりするケースも多くなってくることから、英語でのコミュニケーションができるCFOはより重宝されます。
― 4. 心構え・マインドセット
スタートアップのCFOを目指していくうえで、これだけは心がけて欲しい、忘れないで欲しいポイントについて、一部筆者の個人的な経験に基づくものも含まれますが、いくつか紹介させて頂きたいと思います。
一般的に、スタートアップのCFOを志す方々のキャリアとしては、投資銀行、PEファンド、監査法人、FAS、(スタートアップ含めた)事業会社の経営企画などのバックグラウンドが大半であると思われます。どういったバックグラウンドであっても、それまでに培った知識や経験は十分に活かすことができますが、スタートアップのCFOとして、経営の一翼を担っていくうえでは、常にアンラーニングし学び続けながら、時としてプライドを捨て、新たなものを吸収し続けていく必要があります。
特に投資銀行やPEファンドを経験されている方々からすると、スタートアップが思っていた以上にまだまだ未成熟で、慢性的な各種リソース不足に陥っていることに、ギャップを感じられるケースも数多くあります。スタートアップのCFOを志すのであれば、「カオスを楽しむこと」「一から作り上げていくことの楽しさ」「足りないのであれば、自分で何とかする!」といったマインドを持ってやっていくことが重要になってきます。
また各種メディアでは、スタートアップによる大型の資金調達やIPOに関する記事が出ており、それだけを見ていると非常に華やかな世界に見えなくもありませんが、実際の現場は極めて泥臭く、日常茶飯事のトラブル対応、資金繰りや競争環境など、様々なストレスやプレッシャーを感じながら、日々の業務を行っています。特に2021年の年末頃からスタートアップバブルが弾けたとも言われていますが、以前にも増して、IPOによるExitのハードルは上がっています。スタートアップのCFOを志す中では、当然、金銭的なリターンも期待するところではありますが、その優先度を高くしすぎてしまうと、期待を大きく裏切られる可能性も少なくありません。そのため、そうした金銭的リターンを期待しないとまでは言いませんが、それに固執しすぎるのではなく、スタートアップで働くことの他では得難い経験や成長、新たなチャレンジを楽しむ姿勢を持ち続けて頂きたいところであると思います。
― 5. スタートアップCFOの待遇
スタートアップCFOの報酬としては、キャッシュベースの基本報酬に加えて、株式関連のインセンティブが付与されることが一般的です。
キャッシュベースの基本報酬については、企業のステージによって水準は異なりますが、アーリーに近い企業ですと1,000万円前後、ミドル・レイターの企業では1,500~2,000万円程度の水準になるケースが多くなります。筆者の個人的な感覚でいうと、2~3年前よりもスタートアップCFOの報酬水準は徐々に上がってきており、最近では2,000万円を超えるようなオファーを出すケースもあるようです。
また株式関連のインセンティブとしては、ストックオプションの付与が一般的です。2023年にストックオプションの税務上の取り扱いが明確化※されたことで、レイターのスタートアップであっても、非常に低い権利行使価額でのストックオプションの発行が可能となりました(発行体である企業サイドにおいては会計上の論点が残るため、全てのケースで万能であるとは限りません)。これにより、レイターのスタートアップに入社し、権利行使価額が高く、ストックオプションの付与個数が多いケースでは、無償ストックオプションだけだと税務メリットを取り切れないため、有償ストックオプションの付与を検討する必要がありましたが、無償ストックオプションだけで税務メリットを取れる設計も可能となっています。
ストックオプションの付与割合については、シード~アーリー期になればなるほど割合が高く(1~3%など)、レイターステージで入社した場合は0.3~0.5%程度、かなり良くて1%前後になるケースが一般的です。資金調達を行うと希薄化(dilution)が起きるため、一義的には保有割合が減ることとなります。そのため追加でストックオプションが付与されるかどうかについて、事前に確認する必要があります(もちろんパフォーマンス次第ということになるとは思いますが)。
※参考:「ストックオプションに対する課税(Q&A)」P.14以降
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/230707/pdf/02.pdf
その他、株式関連のインセンティブとして、創業者などから生株を譲り受けるケースもあります。ストックオプションではなく、生株を譲り受けることについては、メリット・デメリットの両面がありますので、そちらも踏まえて、入社時に交渉・相談することをオススメします。
生株のメリット
●ストックオプションと異なり、権利行使期間について気にしなくて良い(特にシード・アーリーのスタートアップに入社する場合は気をつけたいところ)
●無償ストックオプションの場合、税制適格要件を満たす必要がある一方、生株の場合は特に何かの条件を満たすことなく株式譲渡益課税となるため、税務面でのケアが特段不要
●VCなどから外部調達を行っている場合、ストックオプションの発行割合が10~15%程度で制限されているケースが一般的です。それにより十分なストックオプションをCFOに付与できない場合、創業者などからの生株の譲渡により、不足分を補完することも可能(但し、株主によっては創業者の持ち分を譲渡することにネガティブな印象を持つ可能性もあるので、譲渡できる割合には限界があります)。
生株のデメリット
●株式を買うことになるので、最初に資金の持ち出しが必要
以前はストックオプションの権利行使がIPOの時にしかできないケースも多くありましたが、最近ではM&AでのExitも増加していることから、M&A Exitであってもストックオプションが行使可能であるかどうかは、必ず確認することをオススメします。
一般的に、投資銀行やPEファンドなどからスタートアップCFOに転じる場合、キャッシュベースの報酬は下がるものの、ストックオプションなどの株式報酬により数億円~数十億円のアップサイドを夢見て、転職を決断されるケースも多いかと思います。実際にはそうしたアップサイドを享受することは確率として低いものの、非常に夢のある話であることは間違いなく、是非とも読者の皆様にもチャレンジして頂きたい一方で、数年後に後悔することのないように、入社時にしっかりとインセンティブ設計については話し合って頂きたいと思います。
――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――
※ご意見・ご感想、筆者へのご連絡についてはお問合せフォームまでご連絡ください。

― 1. 投資家の属性
エクイティによる資金調達を行ううえでは、様々な投資家にアプローチしていくこととなりますが、以下に主な投資家の属性について、説明していきます。
①国内外のVC
最もポピュラーな調達先であり、日本においても数多くのVCが立ち上がっていることから、資金調達の選択肢は間違いなく増加しています。VCによって投資戦略も大きく異なっている(投資するスタートアップのステージ、投資サイズ、投資後のガバナンス体制や支援体制など)ことから、事前によくヒアリングを行うことと、当該VCの投資先の経営者などにレファレンスチェックを行うことをオススメします。
正直なところ、事業が厳しい局面で投資先に寄り添わないキャピタリストもいるという噂は、よく業界に回ってきます。特にアーリーの投資家とは長い付き合いとなり、投資後にずっと良いことばかり続くことは稀であることから、信頼の置ける投資家を見つけていく必要があります。
②事業会社・CVC
特にスタートアップにおいては、知名度や信用力の不足も含めた営業力の不足により、事業成長が頭打ちとなるケースも多いです。特にそうしたケースでは、大手の事業会社を株主として迎え、営業力を強化することで、シナジーを発揮するケースが見受けられます。
また別の回でも詳細は説明しますが、事業会社の傘下にいったん入り、その後IPOを目指す「スイングバイIPO」の事例も最近では増えてきています。
③クロスオーバー投資家(機関投資家)
特に2021年末のSaaSバブルが弾ける前においては、通常は上場株に投資する機関投資家が、未上場のスタートアップ(主にレイターステージ)に投資する事例が数多くありました。SaaSバブルが弾けた後も、引き続き継続している投資家も存在し、例えば香港の投資家であるKeyrockはニーリーやゼロボード、大型IPOで話題になったタイミーなどにも出資しています。
クロスオーバー投資家を迎えるメリットとしては、上場前後において、追加出資も含めた長期的なコミットをしてもらえる可能性があります。通常、IPO時にVCは持ち分の大半を売却するケースが多いが、クロスオーバー投資家の場合は、上場後もそのまま株式を持ち続けることも期待できます。
それ以外のメリットとして、著名なクロスオーバー投資家に投資してもらえたこと自体が対外的なアピール材料になる、といったことが挙げられます。
④PEファンド
PEファンドは原理原則として、投資先の過半数の持ち分を保有することが通常でありますが、グロース投資の一環で、マイノリティ出資するケースもあります。直近の事例としては、KKRによるSmartHRへの出資です。少し前の事例でいうと、同じくKKRによるDataXへの出資やカーライルによるSpiberへの出資などがあります。
またスタートアップに過半数の出資を行う事例が出始めており、直近でいうとEQTによるHRブレインへの出資、Potentia・J-STARによるjinjerへの出資、ポラリスによるストックマークへの出資などが挙げられます。
PEファンドから出資を受けるメリットは、特に過半数の出資を受けるケースにおいて、ハンズオンで支援を受けられ、PEファンドが持つ様々なリソース(資金調達や人材ネットワークなど)を活用することができることです。また、株主が分散しているのに比べて、株主を集約することで、スピーディに意思決定を行っていくことも可能となります。
一方でデメリットとしては、過半数の出資を受けた場合は、PEファンドの影響力が強くなり、創業者の一存で物事を全て決めていくことは基本的にできなくなります。事業の方針やIPOを含めた資本政策の方針でコンフリクトが発生するケースもあることから、投資前においては株主間契約で経営方針や意思決定の方法については事前に握っていく必要があるのと、投資後においては良好なリレーション作りに努める必要があります。
― 2. 資金調達のスケジュールや進め方、留意すべき事項
一般論として、資金調達に必要な期間の目安として最低でも6ヶ月程度と言われることも多いですが、金融市況の変化など外部環境は移りやすいものであることを勘案すると、もう少し余裕を持って動き始めるのが理想となります。具体的なプロセスについて、順を追って説明していきます。
①ファイナンス方針の策定
まず行うべきは、CEOと今回のファイナンスで目指す調達額やバリュエーション、その他条件について、認識を擦り合わせるところから始まります。ここはCEOのキャラクターに依るところでもありますが、資金使途が不明瞭であり、とりあえず大きく調達しておくといった形で、アグレッシブすぎる調達額及びバリュエーションの水準になっている事例も散見されます。高すぎる水準で調達すると、その後のラウンドでのファイナンスやExit時のバーがどんどん高くなってしまい、今後の資本政策の足枷になってしまう可能性もあることから、投資家とのコミュニケーションも重ねつつ、あくまでもフェアバリューでの調達を心がけることが重要です。
②各種資料の準備
1.プレゼン資料
投資家向けのプレゼン資料については、面談用のやや簡易的なものと、さらにフェーズが進んだ際のより詳細な資料の2パターンを用意することがオススメです。また、海外の投資家にアプローチする場合には、先に英語版を用意し、それを日本訳する方が資料の体裁を整えるという観点では楽になります。
投資家向けのプレゼン資料については、以下のような要素を盛り込むのが一般的です。
1)会社概要(経営陣の略歴やミッション・ビジョンなどを含む)
2)事業内容・競争優位性
3)マクロ環境・競争環境
4)成長戦略・事業計画
5)財務数値・KPI
それ以外にも、「逆に自分が投資家だったら、どんなことを聞くだろうか」というような視点で、資料を準備しておくのと、投資家とのコミュニケーションを重ねる中で、少しずつ資料を追加していきます。
2.契約書
初回プレゼン後に、初期的な検討資料及びデュー・デリジェンス用の資料を開示する上で、秘密保持契約書(NDA)を日英の両方を用意しておきます。その他、実際の投資契約書のドラフトについても、過去ラウンドで締結したものをベースに徐々に準備を進めておいた方が、その後のプロセスをスムーズに進めることができます。海外投資家との契約書を日本語にするか、英語にするかは投資家の意向次第ではありますが、基本的には日本語ベースで対応した方が、他投資家とのコミュニケーションも含めて望ましいです。
3.RFP (Request for Proposal)
CEOと事前にすり合わせた内容に沿って、作成していきます。調達額や株式の評価額、投資後のガバナンス体制など、絶対に譲れないポイントについては、漏れなく正直に記載していきます。DDなどのプロセスがかなり進んだ後に、「こんなはずではなかった」「思っていたのと違った」といった形で双方の認識相違によりプロセスがストップすることもありますが、RFPを充実させることで、双方にとって無駄な時間やコストを費やさないようにしていく必要があります。
4.DD用の資料
Google Driveやboxなどのツールを使って、投資家がDDの際に開示を要求してくると思われる資料を事前に準備しておくと、その後のプロセスが円滑に進みます。もし上場準備が進んでいる企業であれば、主幹事証券会社から要求される資料の最新版を整えておくと、かなりの部分を流用することが可能となります。
③投資家へのアプローチ
投資家へのアプローチ方法としては、
1)既存株主からの紹介
2)金融機関(主に証券会社)からの紹介
3)リンクトインなどでの直接アプローチ
などが挙げられます。
紹介してもらう場合には、ティーザーのような形で、1~2ページで端的に会社概要や事業概要が分かるようなものを用意しておくと、紹介元の人も投資家に説明がしやすく、紹介してもらいやすくなることが期待されます。
また本命の投資家には序盤にアプローチしないことをオススメします。初期の頃はプレゼン自体がまだ洗練されておらず、投資家とのコミュニケーションを繰り返すことで徐々にブラッシュアップされていくものであることから、絶対に入って欲しい投資家は少し後回しにして、プレゼンに一定自信がでてきたからコンタクトを取ることがオススメです。
④DD対応・クロージング
基本的には通常のM&A・資金調達の時と同様の対応であり、スタートアップならではの対応といったものは少ないですが、特にKPI関連の開示については、管理体制が脆弱であると、事業計画や決算書の数字と整合性が取れていなかったりするケースもあります。そうなると投資家からの信頼を失う可能性もあるため、事前に各種経営数値についてはしっかりと整備をしておきたいところです。
また、CEOやCFOだけでなく、COOやCTOなどの他経営陣とのインタビューやプロダクトのデモなどを依頼されるケースも多いです。そういった場合には、事前にエクイティストーリーを中心に投資家とどのようなコミュニケーションをしているのかを説明し、投資家向け説明の整合性がきちんと取れるような振り付けを行っておく必要があります。
当然のことではありますが、資金調達は契約書の締結ではなく、キャッシュが銀行口座に入金されて初めて完了となり、できるだけ前倒しでプロセスを進めるべきです。スケジュールに余裕を持って進めている間に、金融市場などがクラッシュし、契約締結後にご破算となるケースも存在します。キャッシュが入金されるまでは気を抜かずに最後までやり切る必要があります。
⑤PR
資金調達のリリースは、スタートアップにとって最もニュースバリューの高い話題の1つであり、各種メディアへの露出や人材採用においても、戦略的に効果的な打ち出しをするべきであります。
― 3. 資金調達後のガバナンス体制やレポーティング(VCとPEの違いなど)
投資家の属性によって、調達後のレポーティングが大きく異なるといったことはないですが、相対的にPEファンドの方がKPIなどの数字面については、より細かい粒度でのレポーティングが求められます。
またガバナンス体制については、リードVCであれば役員を1名派遣するといった条件を付けることも多いですが、PEファンドになると、基本的には取締役会の過半数を取りに行くケースが多く、また必要に応じて、常駐/半常駐のような形で人員が派遣されるケースもあります。その他、PEファンドの方が各種投資などの経営における意思決定についても、株主の事前承諾事項をより細かく規定するケースも少なくないです。
上記は一般的なケースであって、実際はPEファンドと一言で言っても、ファンドによって色は大きく異なります。PEファンドからの出資受け入れを検討する際には、ファンドや担当者のレピュテーションを調査しておくだけでなく、投資前の段階で特に重要な事項については契約書に規定するなどして、投資後にネガティブサプライズが発生しないための工夫を行っていく必要があります。
――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――
※ご意見・ご感想、筆者へのご連絡についてはお問合せフォームまでご連絡ください。

IPOは依然としてスタートアップにとって有力な資本政策の1つであります。IPOに向けては2~3年程度、あるいはそれ以上の準備期間が必要であり、社内外の関係者をチームアップしながら、数々の困難に向き合いながら実現していく、一大プロジェクトであることに間違いありません。上場準備そのものは、スタートアップであろうがなかろうが、大きくやることは変わらないものの、準備を進めていくうえで取り巻く環境やリソースは、スタートアップとそれ以外で異なる側面もあるため、特にスタートアップがIPOを目指していくうえで留意すべき事項について、今回は触れていきたいと思います。
― 1. 社内外の体制整備
IPOを目指していくうえでは、社内のバックオフィスチームの構築が必須となりますが、特に経理チームについては、若干のバッファを持った採用を行っていくことをオススメしています。というのも、経理チームを最少人数で対応していると、1人でも辞めてしまった場合や、体調不良などによりメンバーが離脱してしまったことにより、IPOが延期になったというケースを何度も聞いたことがあります。
上場準備は、推薦証券となる主幹事証券会社の公開引受チームと連携しながら進めていくことになり、一定の勘所を分かったIPO経験のある人材がいるのであればそれに越したことはありませんが、仮にそういった人材がいない場合には、IPOコンサルの活用もオススメしたいです。上場準備そのものは一過性の事務負担であり、いつストップするかも分からない非常に不安定なものであるから、正社員で全てを賄おうとするのは、採用そのものが大変であることも勘案すると、必ずしも合理的な選択とは言えません。最近ではIPOコンサルも増えてきており、実際にIPOしたスタートアップの支援実績も積み上がっていることから、こうしたコンサルに相談してみるのも一案であります。
その他、IPOプロセスにおいて欠かせない関係者として、監査法人及び主幹事証券会社のリテインが必要となります。ここ数年は、スタートアップ各社がIPOに向けて準備を行っているものの、グロース市場の市況感が引き続き厳しいことと、過去に高い評価額で資金調達を行ってしまったために、IPOを延期し続けているスタートアップも少なくありません。それに伴い、監査法人や証券会社としても、対応しなければいけない顧客数が増える一方であることから、スタートアップ企業がアプローチしても、お断りされてしまうケースも数多くあります。監査法人や主幹事証券会社をリテインするためには、自身の会社がいかに優良企業であるかについて、投資家にプレゼンするのと同様の熱量で説明していく必要があります。
なお、監査法人については所謂Big4以外の監査法人をリテインし、IPOを実現しているスタートアップも増えていることから、大手だけに固執せずに、中堅監査法人をリテインすることも検討可能であります。
― 2. 上場準備上の主要な論点
① 決算の体制
IPO後は、毎四半期末後45日以内に決算を開示する必要があり、よっぽどのことがない限りこのスケジュールは絶対守らなければならないことから、上場審査において決算開示の体制が整っているかどうかは、最重要論点の1つとなります。
前述の通り、経理チームについては、やや人員に余裕を持たせるとともに、場合によっては外部のアドバイザーも一部活用しながら、体制を整える必要があります。
② 予実の精度・予算管理体制
予算に対して、実績がどれだけ差異があるかについては、審査期間中にしっかりとモニタリングされます。基本的には、上振れすぎても下振れすぎても、指摘を受けるが、そうは言っても下振れの方が問題視されることから、基本的には売上は保守的に、コストも若干のバッファを持ちながら、予算を策定しておくべきであります。とはいえ、あまりにも保守的すぎると、バリュエーションの水準にも影響を与えるため、ここは両睨みのバランスで最終的な水準を決定していく必要があります。
また特に赤字上場を目指す場合には、黒字化の蓋然性について、可能な限り定量的に示していく必要があることから、予算のロジックや根拠となる各種数字について、より厳しく審査で見られます。ここはアートとサイエンスの世界ではあるが、いかに目指したい水準感とロジックをうまく組み合わせていけるかが、CFOの腕の見せ所になります。
③ 労務管理
勤怠管理(36協定の違反有無)、未払い残業の有無は、特に上場審査で見られるポイントとなります。よく聞く話としては、親会社はしっかりと対応できていたものの、子会社で重大な違反があるということが、審査のプロセスで判明することも少なくないので、子会社も含めてできるだけ現場への浸透に時間をかけながら行っていく必要があります。
④ M&Aを直前に実施した場合
上場審査中にM&Aを実施し、特に子会社化した場合にはその子会社の内部管理体制についても審査対象になるのと、業績にどういった影響を与えるのかについても精査する必要があることから、対象会社の事業規模やM&Aストラクチャーにもよりますが、上場審査プロセスの長期化も含めて、一定の影響を与える可能性があります。
M&Aを行う際には、主幹事証券会社と密に連携を取って、上場審査プロセスへの影響を極力少なくする方法を検討すべきですが、1つのやり方として、株式譲渡ではなく、事業譲渡によって対象事業を買収することも一案であります。それにより子会社管理体制の論点を1つ消すことができ、かつ、株式譲渡と比して買収後のリスクを低減することも可能であることから、事業譲渡でも対応可能なケースにおいては選択肢の1つとして頭の片隅に入れておいたほうがよいと思われます。
※参考:経済産業省「スタートアップのM&Aに関する調査」(2024年6月24日)
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/r5reportforstartupgrowth/r5reportforstartupgrowth_MA.pdf
― 3. IPOのストラクチャー
IPOの話となると、IPO準備にフォーカスされがちですが、どのようなストラクチャーでIPOを行っていくのかに関するファイナンス戦略も、当然のことながら極めて重要になります。以下に、いくつかの主要論点について、紹介していきます。
①国内オファリングとグローバルオファリング
IPO時のオファリングサイズ(売出し+公募)が大きい場合や、IPO時はそこまで大きくないものの、IPO後を見据えた上で、海外投資家を入れたいケースにおいては、旧臨報方式(国内オファリング)かグローバルオファリング(144A and/or Reg S)の2つの選択肢が存在します。旧臨報方式は目論見書の英訳が不要であり、グローバルオファリングと比べてもコストを大きく抑えられる、かつ、旧臨報方式であってもかなりの数の海外投資家にアプローチ可能であることから、旧臨報方式を選択するケースも非常に多くなっています。想定時価総額が最低でも1千億円前後の水準であり、オファリングサイズもそれなりに大きいケースにおいては、グローバルオファリングも選択肢になってきます。
②親引け・IOI
IPOにおいては、上場前後のモメンタムの形成が、その後の株価形成において極めて重要となります。端的にいうと、需要と供給のバランスを見ながら、需要の方が高い状態を作り出すことと、「人気銘柄である」という印象を植え付ける必要があります。
親引けのように、IPOのタイミングで一部の投資家に一定割合の株式を割り当てることが確約されている形や、ロードショーのタイミングで有力な機関投資家から株式の買付に高い関心があることを公表するIOI (Indication of Interest)などを活用することで、上場前後のモメンタムを形成していくことも有効な手段である。
③投資家とのコミュニケーション(インフォメーションミーティング、ロードショー)
東証の上場承認がおりた後、ロードショーが始まりますが、わずか2週間程度しか期間がなく、かつ、1投資家あたりに1時間程度しかアポイントはセットされないのが通常であります。つまり、ロードショーだけで全ての有力な投資家にアプローチするのは現実的ではないことから、上場前のインフォメーションミーティングや、さらにそれ以前より有力な投資家には定期的にアプローチし、事業の状況等について情報を入れておくことが重要となります。
その際に、ただ闇雲にアポイントを入れてしまうと、「ついこの前話しを聞いたから、今はいいや」といった感じで肝心な時にアポイントが取れないこともあり得るため、特に有力な投資家とはコンタクトするタイミングにも気をつける必要があります。
④オファリングサイズ
売出と公募の合計金額であるオファリングサイズをどの程度の水準にするのかは、極めて難しい問題であります。基本的にはオファリングサイズを大きくした方が、流動性が高まり、機関投資家も投資しやすいので、大きいに越したことはないが、大きすぎると需給のバランスが崩れ、IPO後の株価形成に苦戦することもあります。
またこれはなかなか対処が難しいところではありますが、同じような時期に大型のIPOがあると、投資家がIPO銘柄に振り分けられる配分がそちらに吸収されてしまい、自社のIPOにおいて投資家が入りづらくなるといったことも起こりえます。
既存株主の意向やその時々のマーケットの状況、投資家の”appetite”などを総合的に勘案し、オファリングサイズを決定していく必要があります。
なお、既存株主にPEファンドがいる場合は、事前譲渡により、PEファンドの持ち分比率をIPO前に下げておくことも一案であります。PEファンドが株主であるIPO案件は、上場後のパフォーマンスが不調であるケースも多いのですが、その1つの要因として、IPO時にPEファンドが売却する持ち分が大きく、需給のバランスが悪くなることが挙げられます。そうした事態を避けるために、IPO前にPEファンドの持ち分比率を下げ、IPO時点の需給バランスを整えることで、IPO後のパフォーマンスを良くする狙いがあります。
― 4. その他Tips
東証の上場承認がおりローンチした後に、IPOのプロセスを取りやめるケースが年に数件発生しています。基本的にはロードショーを通じて、バリュエーションの目線が合わないことから取りやめるケースが多いという認識ではあるものの、少なからず東証への通報(いわゆるタレコミ)があり、そちらの重要度が高く、確認に時間を要するような事象である場合には、IPOを延期するという判断となるケースも散見されます。
こうした形でIPOを延期する事態を避けるために、事前に通報される可能性のある事象を洗い出し(元従業員や競合企業、取引先とのトラブル etc.)、それぞれの事象が問題ない旨の書面を弁護士事務所から一筆を入れてもらったうえで、証券会社や東証に事前に説明し、サプライズにならないように工夫をしている企業もあるようです。
――――――――――――――――――――――――――――――
【簡単1分】💻無料転職支援サービスはこちら
――――――――――――――――――――――――――――――
※ご意見・ご感想、筆者へのご連絡についてはお問合せフォームまでご連絡ください。

従前より、上場したメガベンチャーの成長戦略として、M&Aを活用していく事例は多々ありましたが、最近では未上場のスタートアップ企業でも、M&Aを活用する事例が増加しています。その背景には、スタートアップの資金調達環境が厳しい、かつ、単独での成長に限界を感じているスタートアップが増えていることも一因にあると考えられます。今回は、スタートアップをM&Aしていくうえでの、ソーシングからエグゼキューションのプロセス、その後のPMIプロセスなどについて、説明していきたいと思います。
― 1. M&Aの目的
スタートアップがM&Aを行う目的の代表例として、
1)プロダクト・サービスのラインナップ拡充
2)組織ケイパビリティの強化・獲得
などが挙げられます。特に1については最も多い理由となり、例えばマネーフォワードは、SaaSプロダクトの拡張文脈での買収だけでなく、保険代理店を買収するなど、サービス面の拡充においてもM&Aを活用しています。
2の組織ケイパビリティについては、「アクハイアリング」とも呼ばれる人材の獲得や、ネットワークやノウハウの獲得を主目的としたM&Aであり、freeeがフィリピンの開発会社を買収した事例があります。その他変わり種としては、shippio(貿易業務のクラウドサービス)が通関業のライセンス獲得を目的として老舗の通関業者の買収を行うといった事例もあります。
― 2. ソーシング
M&Aのソーシングを行っていくうえでは、以下のようなルートがあります。
① M&A仲介会社
とにかく紹介数が圧倒的に多いことにメリットがあります。また仲介会社によっては一定のフィーの支払い、もしくは、無料で、ターゲットリストの作成やコールドコールによるアプローチも行ってくれることもあるため、ソーシングの社内リソースが不足しているケースでは、有力な選択肢になります。但し、仲介手数料のコストが発生するので、その分のコスト増は留意する必要があります。
② 金融機関(銀行・証券会社)
特に銀行はスタートアップ各社と何かしらの接点を持っているケースが多いため、アプローチできる範囲が非常に広いことにメリットがあります。留意すべきポイントとしては、銀行員の方々も大変忙しく、あらゆるスタートアップから候補先を紹介して欲しいと依頼されているため、うまく進めないと後回しにされ、なかなか紹介してもらえないといった事態も発生します。
そのため、下記のような工夫をしていくことが重要となります。
1.ターゲット先はできるだけ明確に
2.定期的にコミュニケーションを取る
3.M&Aの実現可能性が高いと印象付ける
こういった工夫をしていきながら、win-winの関係性を構築し、円滑なソーシングを実現する必要があります。
③ VCなどの株主
大半のVCはホームページ上で、投資先を掲載していることから、VC経由でターゲット先にアプローチすることが可能であります。最大のメリットは、VC経由で鮮度の高い情報を入手できることと、ターゲット先のライトパーソンにコンタクトすることが可能であることが挙げられます。また、M&A仲介会社などと異なり、仲介手数料のコストも発生しないため、スタートアップをM&Aするのであれば、最も有力な選択肢となります。
④ 直接アプローチ
特にスタートアップの経営者であれば、何かしらSNSなどのアカウントがあることが大半であり、SNS経由で直接連絡を取ることも考えられます。非常に効果的なやり方ではあるものの、資本政策はそもそもが極めてセンシティブなトピックであり、M&A(買収)ありきでコミュニケーションを取ると、場合によっては相手が引いてしまうこともありえるため、アプローチの仕方については十分にケアしていく必要があります。
― 3. デュー・デリジェンス(DD)
一般的なM&Aでも行われるDDプロセスとして、会計・税務DD、法務DD、ビジネスDDは当然に実施するとして、(業種やビジネスモデルによって様々ではありますが)特にスタートアップの買収においては、下記のような事項については入念に調査していく必要があります。
①システム(開発環境など)
買収後にどのような絵姿を描くかによって重要性は変わりますが、例えばSaaSプロダクトを完全に統合していくことを想定している場合には、開発言語や開発インフラなどの環境の違いが大きいと、統合プロセスが長期化する、あるいは、途中で頓挫する可能性もあります。またエンジニアの得意領域が異なることで、アクハイアリング的な人材獲得のメリットも薄まってしまう可能性があることから、どういった開発環境、エンジニアのスキルセットなのかどうかは、DDの中で詳細に確認する必要があります。
②セキュリティ
特にクラウドのプロダクトを有する企業を買収する際には、非常に重要な論点になります。情報漏洩などを起こした場合、買収した企業のみならず、買い手の企業価値の毀損にも繋がる可能性があります。実際に、カオナビが買収した企業が情報漏洩を起こしたことで、カオナビの株価が急落した事例もあります。
PマークやISMSなどの認証を取得しているかどうかをチェックするだけでなく、その他どういった安全措置を講じているのかについて、入念に確認すべきであります。
③企業カルチャー・従業員の離職状況
特にスタートアップの買収においては、有形資産ではなく、人員やノウハウなどの無形資産を買収する文脈が大半であることから、後述するPMIプロセスも見据えて、経営陣との相性や組織カルチャー、従業員の働き方などについて、各種インタビューやレファレンスチェックなども通じて、解像度を高めていく必要があります。こうした情報は、単純に相性を見極めるだけでなく、投資後も見据えて、投資ストラクチャーやインセンティブ設計などにも影響を与えてきます。
― 4. 条件交渉・ストラクチャー
スタートアップの買収においては、評価額の目線が売り主と買い主で大きく乖離するケースが少なくありません。これを解決するための手段として、「アーンアウト」(支払対価を業績等に応じて分割して支払う取引契約)を契約に盛り込むことも一案になります。今後の業績に自信のある創業者及び経営陣にとっては、アップサイドも狙えるため、ケースバイケースではありますが比較的受け入れやすいものになります。また買い手としても、経営陣のリテンションにも繋がるため、積極的に取り入れたいものと思われます。一方で、VCを中心とした他株主が多数いる場合においては、自分たちの影響力がより小さくなる可能性がある中で、業績連動型の分割支払になることを合意形成していくのは一定のハードルになることから、綿密なコミュニケーションが求められます。
ストラクチャーについては、「第3回:IPO準備と管理体制の構築、IPOストラクチャー」にも記載した通り、株式譲渡だけでなく、事業譲渡などのストラクチャーについても考慮すべきであります。通常、事業譲渡はリスクヘッジの観点では有用であるものの、手続きの煩雑さがデメリットでありますが、サイズの小さいスタートアップを買収する場合には、手続きの煩雑さがそこまで大きくないのと、特に管理体制が脆弱である場合には、コーポレートリスクを遮断する観点でも、取りうる選択肢となります。背景は分かりませんが、SmartHRは事業譲渡によりメタップスクラウドをM&Aしている事例もあります。
逆に、PMIプロセスにも密接に関連しますが、別法人にしておいた方がいいケースも考えられます。特に企業カルチャーや報酬体系が大きく異なっているようなケースにおいては、別法人として分けて経営をした方が得策である場合もあります。
― 5. PMI
最も重要かつ難易度が高いのが、PMI(Post Merger Integration)のプロセスになります。特に人材が最大の資産であるスタートアップのM&Aにおいては、経営陣や従業員のリテンションをどのように高めていくのかについては、買収ストラクチャーの検討も含めて、最重要論点と言えます。前述の通り、別法人にするのか、完全に同一法人として統合するのか、インセンティブ設計をどのように行うのか、役員派遣も含めてガバナンス体制をどのように行うのか、それ以外にも、従業員の働き方(出社メイン vs リモートメイン)などといった細かい点においても、十分に配慮していく必要があります。
PMIの一環で、企業カルチャーを無理やり合わせに行こうとする事例も散見されますが、カルチャーの統合は目的ではなくあくまでも手段であり、全ての事例においてカルチャーを合わせにいくことが最適であるとは限りません。特にスタートアップにおいては、双方ともに創業オーナーのもとで強烈なカルチャーを構築しているケースも多く、それを合わせにいくこと自体に無理があります。カルチャーに違いがあるのは当然のものとして受け入れ、人材交流などを通じて、お互いにリスペクトを持ちながら、双方のやり方を学ぶ姿勢を持つことで、PMIプロセスを円滑に進めることができます。
なお、こうしたPMIに関する各種戦略や施策については、投資前のタイミングで、できるだけ細かく双方で合意しておくことが重要になります。実際にはディールをやっている最中は、評価額や契約内容の交渉など、様々な利害関係が入り混じり、本音で会話することは難しいものではありますが、投資後の長い付き合いを考えると、このタイミングでできる限り腹を割って会話し、信頼関係を構築することが、その後の円滑な事業運営と企業価値の最大化に繋がっていきます。
――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――
※ご意見・ご感想、筆者へのご連絡についてはお問合せフォームまでご連絡ください。

従来は、スタートアップのExitといえばIPOが主流であったものの、グロース市場のマーケット環境が引き続き厳しい状況の中で、非常に小さい時価総額でのIPOが数としては多くなっているのが現状であります。時価総額が小さいと、機関投資家から投資を受けるのが難しくなるため、アフターマーケットにおいて株価を上げていくのが極めて難しくなります。また、流動性が少ないのでエクイティによる資金調達の難易度が高く、デットによる調達か自社が生み出すキャッシュフローの範囲内でしか投資ができず、IPO後に成長が減速してしまうケースも散見されます。こうした「スモールIPO」の問題について指摘されている一方で、それ以外の手法でExit(厳密にいうと完全なExitとは限らないが)する事例が国内のスタートアップシーンにおいても増えてきており、具体的な事例も交えながら紹介していきます。
― 1. 事業会社へのM&A
事業シナジーのある事業会社へM&Aで株式を売却するというExit手段であり、ここ数年で最も大きな事例としては、PayPalによるPaidyの大型買収が挙げられます。
事業会社へのM&Aにおいて留意すべき点としては、「のれん」の問題が挙げられます。スタートアップは往々として純資産が非常に薄いケースが多く、その場合、買収金額が大きくなればなるほど、のれんの金額が大きくなります。JGAAPではのれんは定額償却されることから、買い手となる事業会社がのれん償却負担を嫌い、買収に及び腰となることが十分に考えられます。日本において数百億円規模のスタートアップのM&Aがほとんど行われていないことの一因であると考えられます。
― 2. スイングバイIPO
上記の事業会社へのM&Aからの進化形として、事業会社に持ち分の全部または一部を売却し、事業会社との事業シナジーを創出した上で、IPOを目指していく「スイングバイIPO」というものが、最近のスタートアップ界隈では注目されています。直近の事例としては、KDDIとソラコム、ZOZOとyutori、ヤフーとdelyなどが挙げられます。
シナジーを創出し、業績が拡大した上でIPOするということで、これ自体は非常に素晴らしい座組ではありますが、実際のところ、スタートアップサイドの意向通りにIPOできるかは不透明な部分が大きいと言えます。大企業に株式を売却する際に、Exitの時期や方法についても一定は規定することになるとは思われますが、IPOを100%確約させるような文言にするのはなかなかハードルが高く、現実的には大企業の意向によってIPOが実現しないケースも十分にあり得る点については、留意する必要があります。
― 3. PEファンドへのM&A
こちらも最近のスタートアップ業界で注目されている座組として、PEファンドがスタートアップに過半数の出資を行う事例が出始めています。少し前でいうと、アドバンテージ・パートナーズによるネットプロテクションズの買収、直近でいうと、EQTによるHRブレインの買収やPotentiaとJ-STARによるjinjerの買収などが挙げられます。
PEファンドが株主になるメリットとしては、PEファンドの各種リソースを有効活用できる点や株主集約による意思決定スピーディの向上などが期待されます。また、必ずどこかでPEファンドはExitする必要があり(通常は3~5年程度)、創業者や経営陣がIPOを目指したいケースにおいては、IPOを引き続き目指すことが可能であります。
一方で、過半数の持ち分をPEファンドに持たれることにはなるので、従前ほど自由に経営の意思決定を行っていくことは難しくなるので、いかに信頼関係を構築するのかと、株主間契約書で経営方針や意思決定基準、Exitの考え方などについて、細かく規定していくことが必要となります。
― 4. M&AによるExitにおいて留意すべき事項
資金調達の時と同様、M&Aにおいて譲れない点・譲れる点は、創業者と事前に明確に合意しておくべきであります。特に譲れない点については、RFPを作成する際にきちんと盛り込み、買い手候補先に事前に伝えたうえで、プロセスが後半まで進んだ後にハードな交渉とならないようにすることが重要であります。また株主間契約書などの契約書にも、譲れないポイントを明確に盛り込む必要があります。
特に下記のような点については、事前に整理し、できるだけ具体的に買い手候補先と認識を合わせておきたいポイントとなります。
1)ガバナンス体制(取締役会の構成や意思決定プロセスなど)
2)経営方針(何にどれだけ投資するか、具体的な経営戦略の内容など)
3)役職員が保有するストックオプションや株式の取り扱い
4)投資後の役職員向けのインセンティブ設計
5)Exit方針(Exit手段やタイミングの考え方)
― 5. デュアルトラックのプロセス
IPOをメインシナリオとしつつも、デュアルトラックでM&AによるExitの可能性についても模索することをぜひオススメしたいです。IPOは自社の業績だけでなく、マーケット環境にも大きく左右されることから、自分たちが理想とするような形でIPOできるとは限らないですし(逆にそうしたケースの方が少ないと思われます)、IPOよりも高い評価で買収を検討してくれる事業会社や投資家がいる可能性も十分にあります。また仮にそういった先にいったん売却したとしても、もう一度IPOを目指すことも可能であります。
デュアルトラックを行っていくうえでは、IPOの上場審査を対応しつつ、M&AのDD対応もセットで対応する必要があることから、対応メンバーは多忙を極めることになります。少しでも対応を省力化するためには、管理メンバーを充実させるだけでなく、IPOの外部コンサルを活用することや、内部の各種資料を定期的に整理しておくことで、上場審査とDD対応をほぼ同じ資料で対応するといった工夫も行うべきであります。
いずれにせよIPOありきで物事を進めるのではなく、それ以外の可能性についても常に模索しながら、最適な資本政策を追求していくことが必要となります。
スタートアップのCFOは、資金調達やIPO、M&Aなどといったファイナンス的な知見や経験は当然のことながら、スタートアップの経営陣の一角として、事業成長への貢献や組織拡大フェーズにおけるカルチャー作りなど、経営者としての側面もあり、非常に希少性の高い人材であることに疑う余地はありません。スタートアップでのCFOの経験を活かして、その後のキャリアをどのように築かれているのかについて、実際の事例も交えながら、紹介していきます。
― 1. スタートアップのCFOを経験することで得られるもの
ファイナンスやM&A、IPOなどは、スタートアップのCFOでなくても、投資銀行やPEファンド、戦略コンサルなどでも、数多く経験することができます。一方で、筆者自身の体験としても強く感じたところですが、スタートアップのCFOとして働くことは、圧倒的な当事者意識が必要であり、自分の意思決定や行動が、そのスタートアップの事業拡大の成否に大きな影響を与えます。その過程で、得た知識や経験、スキル、ネットワークなどは、その後のキャリア形成においても、間違いなく大きな礎となっていきます。
また企業経営をしていくと誰しもが直面する困難として、ロジカルでもっともらしい戦略や戦術はいくらでも描くことはできるものの、それを実現するための実行プロセス(エグゼキューション)の方が圧倒的に難易度が高いということであります。自分1人でできることには限界があるため、多数の社内外の関係者を巻き込みながら進めていくこととなりますが、その過程で、強いリーダーシップ・人間力・胆力といったソフトスキルも鍛えられていきます。
― 2.CFOのその後のキャリア(事例)
他スタートアップのCFO
IPOなどでのExit後に、他スタートアップのCFOに転身されるケースは数多く存在します。特にスタートアップのCFOとして培った資金調達に関するノウハウやネットワーク、IPO準備の経験を次の先でも存分に活かすことができるうえ、Exitにより一定の資産形成ができているケースでは、リスクを取った次のチャレンジを行いやすいとも言えます。
事例:
・newmo 武藤CFO(前プレイドCFO)
・ファストドクター 中川CFO(前ココナラCFO)
・enechain 藪内CFO(前paidy CFO)
投資家
CFOとして経営の一角を担い、事業や組織が拡大していくフェーズを経験することは、投資家としての目利きの観点でも、また投資後のバリューアップの観点でも、非常に有益な経験となります。投資を受けるスタートアップサイドの視点でも、実際にスタートアップのグロースフェーズに携わった方々から投資を受ける方が、投資後のサポートやコミュニケーションが円滑に進みやすいというような安心感を得られるということも期待できます。
事例:
・Minerva Growth Partners 長澤氏(前メルカリCFO)
・Keyrock Capital Management 内河氏(前マネーフォワードCFO)
・Goldman Sachs 松本氏(前SmartNews CFO)
・ミダスキャピタル 寺田氏(前じげん CFO)
CEOや他のロールへの転身
CFOはその高度な仮説構築力や、特に複数プロダクトや事業を営む企業においては、いかに各種リソースを最適にアロケーションするかが最も大きな経営テーマであり、その観点では、CFOとしてのファイナンス思考が最も活きていきます。
事例:
・ラクスル 永見CEO
・フリー 東後CPO(退任済み)
その他
現状では、他スタートアップのCFOや投資家としてのキャリアに転じることが、最も事例としては多いように見受けられますが、それ以外にも、事例としては少ないですが、起業家として自身の会社を立ち上げるケースや、大企業のファイナンス責任者として手腕を振るう事例も存在します。
起業の事例としては、HQの坂本CEOが挙げられます。投資銀行やPEファンドでのキャリアを歩んだ後に、LITALICOのCFOとしてIPOを実現し、その後、HQを立ち上げ、大型の資金調達も実現しています。
また大企業に転身した事例としては、森 暁彦氏が挙げられます。投資銀行でのキャリアの後にレノバのCFOとしてIPOを実現し、現在では、リクルートのファイナンス担当執行役員として活躍されています。
― 3.最後に(スタートアップCFOを目指す方々へのメッセージ)
CFOとしてスタートアップで働くことの最大の醍醐味は、0→1のフェーズも、1→10のフェーズも、非常に大きな裁量を持ちながら推進していくことができることにあります。その過程においては、慢性的に何かしらのリソースが不足しており、時として自分自身がプレイヤーとして前線に立ちながら、物事を推進していく必要があり、辛いと感じる局面も少なくありませんが、否が応でも圧倒的な当事者意識を持つこととなり、様々なハードシングスを乗り越えていくことで、PEファンドや投資銀行、戦略コンサルなどでは味わえない、得難い経験を積むことができます。
日本のスタートアップ・エコシステム全体のことを考えても、様々なバックグラウンドを持った方々がスタートアップのCFOに転身して、IPOやM&Aなどを実現したうえで、また違った形でスタートアップの経営やスタートアップへの投資に関与することによって、エコシステム全体としての厚みが増していくことも期待されます。
今回のコラムを通じて、少しでもスタートアップのCFOとしてのキャリアに興味・関心を持って頂き、実際にチャレンジしてくれる方々が増えてくれることを、心から願っています。
無料転職支援サービス
申込フォーム
(目安時間1分)