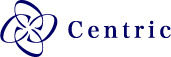【第3回】財務数値の把握のためのプロジェクトについて
Warning: Undefined array key 0 in /home/xs298991/c-centric.jp/public_html/wp-content/themes/c-centric/single.php on line 19
- 2025.04.29
― 1. 背景
ファンド投資チームは投資前のDD(デューデリジェンス)では結果数値の分析は行っているものの、実際の月次決算の作業方法(時間軸・粒度・基幹システムとの関係等)までは投資先に入ってみるまでは不明です。そのため、ファンドでは投資直後から外部の専門家(主に会計系コンサルティングファーム)を使って「財務数値の把握のためのプロジェクト」を走らせることがほとんどです。ファームと投資先の財務経理部門との役割分担は投資先の状況によって千差万別ですが、おおよそ①管理会計の解像度アップと②決算作業の効率化=早期化の二つのパターンがあるように思います。①の場合、ファームが現場にある数値を組み合わせて実績分解を行う「モデルの作成」まで行うことが多い印象です。一方、②については作業工数を減らすための計算シートの作成までをファームが行う場合もありますが、どちらかというとファームはファンドや投資先マネジメントへの「説明資料」を作るのが精いっぱいで、実際の効率化・実務処理の変更はCFOが現場を指導せざるを得ない、というのが私の経験則です。
DDの際に使ったFA(Financial Advisor)の事務所を使う場合もありますし、ハンズオンを売りにしたブティック系ファームから選ぶこともあります。
前回予告から内容を少し変更して、今回はこのようなプロジェクトでの注意点を少し深堀したいと思います。
― 2. 具体的な論点
(ア) 外部専門家の見極め
① ファンドとの関係
いくつも投資を行っているファンドには従来から親しくしているファームがあるものです。気心が知れているということもありますが、ファンドが機関投資家や投資委員会へ報告する際のポイントをわかっていて、いちいち説明が不要ということが大きいと思います。よってCFOは与えられた駒(ファーム)をどう使うかというスタンスでいたほうが良いでしょう。ファーム名は投資先企業が使える費用感・課題感によって差が出てきますが、エスネットワークスさんやリヴァンプさんのほか、監査法人系のFAS部門が最初に名前が挙がるところです。最近はこれらファームを卒業して個人で業務受託を行う方々も増えてきました
② 担当するマネージャーとジュニアスタッフ
実際のプロジェクトではパートナーが統括しその下にマネージャークラスとジュニアスタッフがチームアップ体制図でとなることがほとんどです。
本来、パートナークラスが成果物の「品質」を担保するべきポジションですが、実際にはマネージャークラスに任せきりになるのが通例です。
よってマネージャークラスの実力を見極めどう使うか、が「将来的に使える成果物」を生み出せるかどうかのポイントとなります。
各人の経験・職歴はCV(職務経歴書:ラテン語のcurriculum vitaeの略とされる)で確認するとして、会計的な知識や資料を作る能力よりも、経理実務にどの程度知見・経験があるか、ということが重要です。
③ どのように使っていくか
このプロジェクトの費用はファンドの指示ではあるものの、投資先負担で行われることが一般的です。ということは形式的にはファームのクライアントは投資先であり、ファンドではありません。よって投資先が将来的に使いやすく意味のある(実務とはなれた、報告のためだけのレポートにならないよう)成果物とするため、CFOはプロジェクトの方向性をリードしていく必要があります。
(イ) 財務会計と管理会計
① 意外と難しい両者の整理
CFOを目指す方であれば両者の違いのご説明は不要と思いますが、意外と実務面で切り分けるのは難しいというのが私の経験則です。これはファンドの方だけでなく、投資先の実務者でも混乱されている方がいます。例として財務会計(及び財務会計システム)では売上の粒度は細かい必要はありません。小売業で日別・ブランド別に売上が立っていたとしても、財務会計では極端な話、月の合計で一本仕訳を起こせばよいのです。日別売上やブランド別、製品別の売上情報は管理会計に属する領域であり、財務会計の外側で明細が取れれば、財務会計では上記の通りまとめて計上で事足ります。実務的に難しいのは、売上先の管理や売掛金の消込を財務会計システムの中で行ってしまっている例が多いからです。そのため、財務と管理がごっちゃになってしまうのです。
② 両者の相反関係
財務会計はできるだけ仕訳を少なくすれば決算は早くしまりますが、管理会計は細かくすればするほど解像度が高まり、具体的な施策につながるため両者は利益相反の関係にあると言えます。
また財務会計は最終的に株主や金融機関など外部への報告数値となりますので正確性(対象期間、段階利益)が求められますが、管理会計は「経営の判断のために必要な情報」であるため、ある程度の割り切りのもとトレンド変化(例:前年比)や横比較(例:店舗間、ブランド間等)ができる数値の集計が必要となります。
(ウ) 決算の早期化
① EXITを見据えた月次決算スケジュール
投資規模にもよりますが、一定程度の規模の投資案件であればIPOもしくは上場企業への売却がファンドのEXITの基本戦略となります。
これはグループ連結の月次決算を四半期ごとに45日で市場に開示する前提で、決算スケジュールを早期化する必要があるということを意味します。
しかもこの日程に間に合うよう、連結や国際会計基準へのコンバージョン、注記情報、開示資料の作成に加えて監査法人からのお墨付き(監査意見書)の取得までを行う必要があります。
② 実務処理能力
投資先企業の準備状況にもよりますが、非上場の会社では単体ベースの決算を締めるのがやっとで、それ以降の作業は全くしていない例が多いです。しかも支払いを間違わないことを優先するために、月次決算を翌々月まで締めないという例もあります。
ファンドの担当者ではこの作業をどのように早めるのか、どこにリソースを追加すべきなのか、そのために処理をどのように変えるのかは皆目見当がつきません。これらの実態把握もプロジェクトのカバーする領域の一つです。
③ 将来の業務改善を見据えて
最近では会計系ファームの担当者でも「具体的に」どのように変化させていけばよいのか、わからない人も増えました。特に大手と言われるファームでは会計士の資格を持っていても、具体的に仕訳を起こしたことがない若手もたくさんいます。CFOはいずれ早期化を主導していかなければならないわけですから、このプロジェクトでより実務に近い処理を把握し、改善の方向性をイメージしておくことはとても重要です。
― 3. ファンドの求める物と実務との調整
(ア) ファンドが求める管理粒度
プロジェクトを進めていく中で、ファンドがどのようなレベル感を期待しているのかを探って調整していくわけですが、基本的にファンドは改善プランの実効性を見えるようにしたいものです。自分たちがバリューアップできると示すことが、ソーシング(新たな投資先候補の探索)やファンドレイズ(機関投資家の資金集め)へのアピール材料になるからです。
よってファンドは財務会計では必要のないブランド別・製品別などの詳細情報を見えるようにしたいニーズを持っています。ブランド別・製品別の「営業利益」やチャネル(店舗・EC・卸等)別・店舗別の「営業利益」を見たいというニーズは分からないでもないですが、細かくすればするほど「共通費の配賦」という問題がでてきて、時系列比較の意味がない数値を作ることになります。
① 悪影響の具体例
AとBという商品・店舗がひとつずつある例で説明しましょう。店舗経費はそれぞれ発生した費用が把握できている(直課可能)。一方、本部人員は両店舗の仕事をやっているため、(工数管理をやればできなくはないものの)正確には分解できない。しかたがないので、AとBの売上の比率で案分(配賦)して営業利益を計算する。翌年は前年に比べてA商品は売り上げ横ばいだったが、B商品は売り上げが倍増した。前年と同じ考え方で営業利益を出すと、Bに多く配賦され、Aの売上実態が全く変わっていないのに、配賦が減った分営業利益ベースでは改善したように見え、BよりAの方が良い製品であるという間違った判断をしてしまうことになるのです。
② 概念の整理
解像度を上げることは良いことですが、CFOはファンドの言うままにモデルをくみ上げる癖が強いファームを、うまくコントロールして、ファームが抜けた後も事業判断に使える数値を計算する成果物を作らせなければなりません。このあたりのバランスは難しいところですが、ポイントは現場が理解して、行動をかえることができることと考えています。最も詳細なデータはトランザクション(例:日々の製品別・店舗別売上)データがあり、これらは現場が日々確認して、手触り感があるものです。これらを積み上げることで大きなトレンドや変化点を実感してもらうことは事業判断に使えると言ってよいでしょう。一方で現場がみていないブランド別利益率などは慎重に検討が必要です。上記の例では、店舗別の経費は取れるが、共通費は工数分解ができないため、正確な経費が計算できないことをファンドに理解してもらい、粗利ベースの比較モデルとするか、直課できる部分のみの比較モデルとするか、はたまた、共通費の売上に対する比率を決めて売上から計算するモデルにするかなど、いくつかのパターンがありえます。ファンドに間違った判断をさせないために、かつ、実務担当者がデータ更新を継続していけるようなモデルにするのはCFOの腕の見せ所と言ってよいでしょう。
私自身はファンドの求める粒度が意味があるものであれば、ファームがいる間にワークシートを作ってもらい、かつ、自分でも更新作業を行っています。逆に意味がないと感じた物は、その理由を伝えたうえで理解を得る努力をし、それでも要求された場合は、その目的を確認、シンプルなロジックを提案・合意をしたうえで数値を作ってきました。
(イ) ファンドが求めるスピード感
① ゴールと実現スピードイメージ
ファンドは常に最終ゴールから逆算で今の状況を見ています。上記にもお示しした通り、最終ゴールは四半期決算・45日開示となります。このゴールにどのように近づくかですが、実績が早く締まればその分改善策を打つ時間が多く取れることになります。
ファンドはROI(投資収益率:Return On Investment)はもとより、IRR(内部収益率:Internal Rate of Return)でも同業他社比較されます。よって「なるべく早く実現する」ということを常に意識しています。
決算早期化についても同様で、遅くとも6か月以内に(はやければ3か月以内)「月次決算が翌月半ばには報告される状態」を実現してほしいと思っておいた方が良いでしょう。
これはどういうことかというと、数値の精度は一定程度の水準を保ちながら、2~5回程度のトライアルで月次決算作業の短縮化を実現しなければならない、ということです。最初の月から仮説をもってトライアルしていく重要性がご理解いただけるかと思います。
② 実務作業者への働きかけ
とはいえ、CFOが全ての作業を一人で、しかも初月から実施できるわけではありませんし、そういう役割でもありません。経理財務は記帳だけでなく回収・支払等の資金移動についても、最後の砦となります。実務を壊さないように、かつ、もともと保守的な人が多い経理財務部門の人たちの業務を改善していくためには、変化に向かってチャレンジしてもらう必要があり、変化を的確に指示するとともに、受け入れてもらうためにも初回で触れた「人間性」(スキル・知見の前に投資先の社員に受け入れられること)」が必要となってくるのです。
(ウ) 実務とのすり合わせの勘所
実際にすり合わせするにあたって、どの程度の水準を目指すかは私自身も毎回悩みます。ご想像の通り、ファンド及び投資先の置かれている状況によって、正解はありません。以下に述べることはあくまで個人の意見ですので、参考にしていただき、ご自身の例に合わせて調整いただけば幸いです。
① ファンドへの説明
まず、ファンドとは粒度や時間軸について、ゴールイメージを共有していること、目指そうとしていることを伝えます。その前提で、投資先の現状を伝えベストエフォートでゴールに近づくよう、実務を変革していくことを伝えています。
くわえて、少しずつでよいので毎月進化していく様を見せるようにしました。
たとえば初月は一部門・一事業のPLを例に、主要科目の計上実態(例:月ズレになっているとか、共通費で計上されているため直課されていない等)を説明。翌月は直課されている費用と配賦すべき金額のボリューム感を説明し、直課するために業務処理を変更しなければならないのか、変更した場合には工数が増えて、早期化の阻害要因になる等をインプット。その次の月は、数か月の傾向を見せて、売上の比率で試算すれば大きなずれは生じないことを検証した結果ことなどを説明というように、部分から全体に広げる場合もありますし、逆に全体の費用構成から説明して、取り組む科目を最初に絞った時もありました。
② 担当者への働きかけ
担当者には「実務が一番重要で、レポートのために実務を壊したら元も子もない」ということを伝えるとともに、「目指すゴールは高く、少しずつでもレベルを上げていかなければならない」ということをはっきり宣言しています。
その際、これを機に経理財務担当者が「直したくても事業側に受け入れてもらえなかったこと」「改善したくても手を付けられなかったこと」を一緒に改善していこう、というメッセージを発信したうえで、実際に自身が泥をかぶることをやって見せています。
いつも通用するかどうかは分かりませんが、泥臭い例をご紹介して本稿を終わりにしたいと思います。
「現場が経費精算や支払依頼を期日通り持ってこない、言っても変えられない」といった経理部員のあきらめの声がありました。これに対して「期日に間に合わなかった提出は『全てCFOが状況を確認したうえで、可否判断をするので、部屋に持ってくるよう』にということを全社に通知するように」と指示をしました。
売上が数百億円を超える会社で、宣言通りすべてをチェックするのは正直大変でしたが(途中で記録をするのをあきらめるくらいのボリュームで、正確な件数は覚えていないのですが、初月は500件は超えていたと思います)、このことで経理の担当者の信頼を得られたことは今となっては良い思い出です。
次回は中期事業計画の立案・モニタリングについてご紹介したいと思います。
――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――
※ご意見・ご感想、筆者へのご連絡についてはお問合せフォームまでご連絡ください。